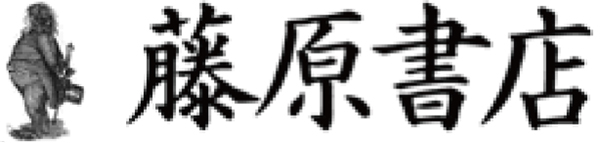前号 次号 社主の出版随想 ▼現在、本を生業としている業界が立ち行かなくなってきている。売上げを見ても、四半世紀前の最盛期の40%近くに落ち込み、書店数も、二分の一に減少している。教養書で、初版3 […]
PR誌『機』記事
前号 次号 社主の出版随想 ▼昨年の出生人口が、72万6千人と発表された。戦後のベビーブーム時の270万人からみると、3分の1を切って4分の1にならんとしている。出生率の問題は、国の将来を見通す根 […]
前号 次号 社主の出版随想 ▼2月に入って、東京も今年初めて雪に見舞われた。ふだん雪のない地は、少しの雪でも交通はじめ色んなことがストップする。1月下旬、札幌から北へ1時間ほどの奈井江町を訪れた。 […]
前号 次号 社主の出版随想 ▼元旦早々、日本列島に大地震が襲いかかった。能登半島に震度7強の凄じい地震。津波や火事の被災もあり、今のところまだ明確な状況は把握されず1週間が過ぎた。地震・火山列島で […]
前号 次号 社主の出版随想 ▼又、大切な人を失った。フランスのアナール派の第三世代の旗手であり、歴史家の巨人、エマニュエル・ル=ロワ=ラデュリ氏。享年九十四。 今から45年前、名著『ナポレオン』『 […]
前号 次号 社主の出版随想 ▼1971年6月、暑い日だった。中之島公会堂は、2千人近い人々で埋め尽くされた。野間宏著『青年の環』(全5巻)完成記念講演会と題された大きな垂れ幕がかかっていた。周囲に […]
前号 次号 社主の出版随想 ▼A氏の訃報が先日届いた。A氏とは、30有余年前、小社出発前からの附き合いになる。A氏は、拙と齢同年で、70年代後半に渡仏し、苦学の後に、仏ボルドー大学教授の職を得た。 […]
前号 次号 社主の出版随想 ▼1978年夏の頃だった。いつもの渋谷の京王レストランでビールを飲みながら、K氏は、『ヌーヴェル・オプセルヴァトゥール』誌を開きながら、今フランスでソ連に関する2冊の本 […]
前号 次号 社主の出版随想 ▼今年も暑い夏である。体温を超える日が何日も続くと、ヤレヤレどころか、この先どうなるんだろうの不安が先に立つ。今8月8日。6日は、一日TVをかけ、慰霊式の実況を観たり、 […]
前号 次号 社主の出版随想 ▼「一に人、二に人、三に人」は、後藤新平の至言である。この世は、すべて人の行動、言動によって生まれる。人が人を生みかつ育てる。すべての営為が人によって構成される。だから […]
前号 次号 社主の出版随想 ▼梅雨入りの季節だ。晴れた日が少ないし、今年は、線状降水帯なる言葉が頻繁に登場し、余りにも1時間単位で天気予報されるだけでうんざりだ。昔のように、「晴れ後曇り時々雨」ぐ […]
前号 次号 社主の出版随想 ▼最近、加藤登紀子さんとお話しする中で、過日凶弾に斃れた中村哲医師のことが話題になった。そこで、不図、中村医師が一目置いていたインド緑化の父 […]
前号 次号 社主の出版随想 ▼久しぶりに沖縄を訪ねた。旧交をあたためることと、最近亡くなった友の供養の旅である。まず、沖縄島に住む安里英子さん。昨年大病を患い、あと何カ月といわれたこともあったが、 […]
前号 次号 社主の出版随想 ▼後藤新平という男が、その時居なかったら今の日本は在るだろうか、とふと思う時がある。日清戦争に勝利して国内は沸いていたが、憲法発布後まだ6年、当時大清帝国では伝染病コレ […]
前号 次号 社主の出版随想 ▼1月も終り、2月に入った。先日、久しぶりに家内を車椅子に乗せ、近所を散歩した。紅梅が咲き誇ってる光景はお見事という他ない程美しかった。蠟梅から紅梅へと、梅はわたしたち […]