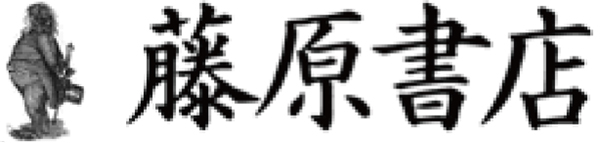前号 次号
社主の出版随想
▼新緑の候だ。近くの善福寺公園の池の廻りを散歩したが、緑の息吹きと“芽生え”を感じるひとときだった。すべての生き物が芽を出し、生まれ出る力が漲っているように思えた。今のこの時も世界のあちこちで戦で街は破壊され、泣き叫ぶ子ども達が映像に次々と映し出される。わが国でも、小さな島々の要塞化が時々刻々と進んできている。
▼沖縄島に棲む安里英子さんが、この3月、闘病生活の末、急逝された。享年75。彼女とは、85年秋、「フォーラム・人類の希望」のイバン・イリイチ氏を囲むシンポジウムのパネラーとして玉野井芳郎・代表幹事の推薦でお呼びした。「沖縄のシマ社会における食文化と女性の役割」について話された。終わった後、司会を務められた鶴見和子さんのお宅で、小宴が催された。英子さんは、沖縄の自然をこよなく愛し、侵されてゆく沖縄で自らミニコミ紙『地域の目』を作っているとその時伺った。その後、数回の手紙のやり取りをした位で音信は途絶えていた。
▼97年秋、小社で刊行した『女と男の時空――日本女性史再考』の完結記念シンポジウムを沖縄でやることになった。それが彼女との再会であった。それ以来、時折訪沖した時は、必ずといっていいぐらい会って意見交換した。08年から始めた、年2回の「ゆいまーる・琉球の自治」(~18年)活動にも積極的に参加してくれた。最近では、やんばるの旅にもご一緒した。芭蕉布の人間国宝平良敏子さん、国頭村の共同店など色々と現地を紹介してくれる存在だった。
▼最後の交感は、新著『琉球 揺れる聖域』出版への序文の依頼だった。その頃は、かなり悪くなっていたのかもしれない。しかし、最後の最後まで、沖縄の土を愛して止まなかった彼女は、90年初頭に出した『揺れる聖域』は、今ではもう読めないので、巻頭に全文載せて欲しいと懇願された。30有余年経った現在の沖縄は、宮古・八重山の小さな島々にも、自衛隊やミサイルが配置・配備され、いつでも戦闘できる態勢を整えている。まさに要塞化されてゆく琉球。安里英子は、半世紀以上、愛する沖縄の有りようを怒りと悲しみに悶え苦しみながら闘ってきた。安らかにお眠り下さい。合掌(亮)
5月号目次
■『玉井義臣の全仕事』(全4巻・別巻一)発刊
玉井義臣 ほか 「世界の「あしなが」へ」
■気鋭の憲政史家の新しい憲法論 『自由主義憲法』
倉山 満 「今こそ、真の「憲法」論議をしよう!」
■三砂ちづる 「八重山へ」
■山田鋭夫 「「ゆたかな富」から「ゆたかな生」へ」
■〈追悼〉安里英子さん
海勢頭 豊 「「聖域を汚染する不条理を許さない女」」
■〈新連載〉日本ワイン 揺籃期の挑戦者1
叶 芳和 「ワイン産業は芸術だ!」
〈連載〉山口昌子 パリの街角から17「通訳は裏切者?」
田中道子 メキシコからの通信14「中立外交と国連改革」
宮脇淳子 歴史から中国を観る53「宗教としての古代儒教」
鎌田 慧 今、日本は61「石垣島の教訓」
村上陽一郎 科学史上の人びと14「ドーキンス」
小澤俊夫 グリム童話・昔話14「北ドイツの謝肉祭と南ドイツの謝肉祭」
方波見康雄 「地域医療百年」から医療を考える36「「涙に他者のいのちあり」」
黒井千次 あの人 この人14「横顔だけの人」
山折哲雄 いま、考えること14「自由の天地へ脱出」
中西 進 花満径98「桃李の歌(1)」
4・6月刊案内/読者の声・書評日誌/刊行案内・書店様へ/告知・出版随想
■PR誌・月刊『機(き)』は、藤原書店ブッククラブの機関誌でもあります。定期ご購読はこちらから
■見本誌のご希望も、お気軽にご用命ください。こちらから