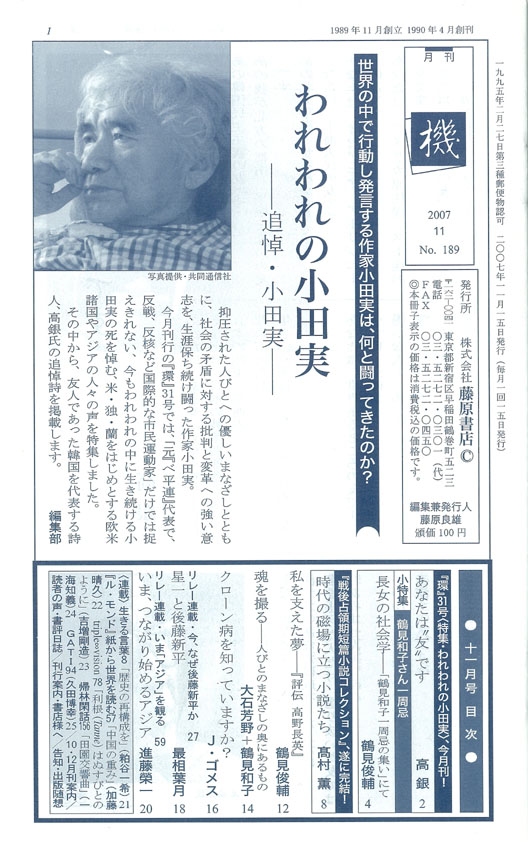小説の空気
小説を読む人は、登場人物の物語を楽しむ一方で、それが書かれた時代や社会の気配を渾然とした生理のうちに感じ取る。とくにその時代がなんらかのかたちでその人の記憶に含まれるとき、一篇の小説はその人のこころのなかでその人だけの枝葉を伸ばし、根を下ろしてゆく。思えば、太平洋戦争とその後の占領期は、2007年のいま現在、わたくしたち日本人がなおもそうして小説の時代を皮膚や身体で感じ取り、生理の奥深くで嘆息することの出来るぎりぎりの年月のうちにある。
もっとも、時代の記憶とは必ずしも実際にその時代を生きたということではない。たとえば1953年生まれのわたくしは、直接には戦争も敗戦後の占領期も知らないが、幼いころに見た父母の表情や物言い、そして戦後の混乱期の面影が色濃く残る町の生活風景を通して、その時代への特別な皮膚感覚が自分にあることを知った。それは父母への迂遠な眼差しと重なっており、いわば父母を透過してやってきた時代の記憶ではあるが、それでも、わたくしの身心に父母の存在が徹底的に刻まれているのと同じ仕方で、わたくしのなかに一定の痕跡を刻み込んでいるのは疑いのないことである。
すべての小説にとって、それが書かれた時代の空気を知る読者が多く存在しているというのは、無条件に幸福なことである。とりわけ、戦争や飢餓や国家の崩壊といった劇的な経験に満ちた時代は、それだけで強力な磁場をもつ。そうした磁場は作家を駆り立て、意思を越えた力が作家に何事かを書かせるということが起こる。そのとき、奇跡のように表現や行間から滲みだして登場人物や物語の空間を浸すものがあり、それをわたくしたちは小説の空気と呼び、力と呼ぶ。また、同時代の読者の場合は、その同じものを共感と呼ぶかもしれない。そして、主題や小説作法とはべつの次元から生まれてくるこの空気は、小説という家のすみずみを彩る照明のようなもので、それによって家がより家らしい空間になって住む人の身体を包み込むのである。しかも、その照明を灯すのは読者の記憶と言語感覚であり、人によって見え方も違う。とりわけ時代の空気はそうである。それを感じ取らなければ小説空間が成立しないというのではないが、小説を読むとき、そこに満ちている時代の空気は、もしも感じられるのであれば感じられるに越したことはない。一つの表現だけで、ある時代の己が人生に伝播してゆく意味の広がり。一行毎にどこからか湧いてきて小説の傍らにこぼれ落ちる私的な感情。そしてまた、それらが次々にふくらんで再び小説の空間に逆流してゆく感覚。すべてが「小説以上の何か」であり、「小説ならではの何か」であり、このとき活字の空間で、作家と、物語と、読者それぞれの或る時代が立ちあがっている。
こころの澱
ちなみに、時代を超えて100年も読み継がれるような小説は、そうした時代の空気という照明を取り除いても十分に住めるような構造と意匠を備えた家でなければならないことになるが、1945年から52年という占領期は、幸いなことにまだ、かろうじてわたくしたちの記憶の範囲内にある。従って、その時代に書かれた小説たちはひとまずそうした年月の評価の手前にあり、しかも敗戦という劇的な経験の磁場が発していた未曽有の力を行間に漲らせたまま、それぞれに初々しい顔をしてわたくしたちに読まれるのを待っていたということになろう。実際、わたくしはここに収められた六篇を今回初めて読んだが、ほとんど古さを感じなかった。それぞれ一篇の小説として立っているだけでなく、むしろ作家たちにとって、占領期がその人生の特別な時期であったことを明かしているような、その時期ならではの作品と呼べるものばかりである。一括りにするなら、庶民生活の混乱とエネルギーの横溢の上に、新しい民主主義社会の一様な薄明るさが載っていた時代、作家としてそれには少し距離を置きながら、戦前戦中に溜まった自らのこころの澱を、庶民に先駆けていち早く吐き出し始めた時期の作品群と言えようか。また、ここに集められた六名の作家たちは当時、いずれも人生のなかでもっとも気力の充実した青壮年であったことから、占領期という特別な時期の短編にも、それぞれに作家としての意気込みと自負が注ぎ込まれているのは言うまでもない。
巨大な違和感と失意
富士正晴の『童貞』は、右のような条件をすべて満たす巧みな作品である。富士の眼差しは、自身が経験した戦時中の生活と人間の片々に向かっているが、あえて衣服や社会的肩書などの被いの下から性をむき出しにさせてみせる、その手口の繊細さに作家の資質は明らかである。富士が描いたのは、戦時中であっても人間の本質はつまるところ下半身だったというふうな話ではない。作戦指揮も、戦闘能力も、兵站も何もかもお粗末で悲惨だったと言われる日本の軍隊にあって、前線の兵士たちの滑稽かつ無軌道な性欲処理のありさまを描いたのでもない。作品にあるのは、当時応召して軍隊に入った多くの一般人男子の一人として、己が全身で味わった巨大な違和感と失意のかたまりの核心を探らんとする小さなこころの営みが、ふと立ち返ってゆく先としての人間の顔であり、姿であり、下半身である。それこそ作家というものであるが、一兵卒の富士が大陸で出会った年下の少年下士官は、たとえば「怒りっぽい美食家」「田舎の小学校の級長」「未だ女の身体を知らぬものの潔癖」などと形容される。残忍と貴族的な律儀さ。潔癖と美食。容赦のなさと童貞。そうした生命として作家が見つめる一少年下士官の肖像は、戦前の日本の地方出身者の精神性や、田舎の青年たちの上昇志向を軍国精神に仕立て上げた帝国陸軍の何たるかを透かして見せるだけでなく、日本の近代への哀しみを感じさせて、ああそうかもしれないと読後の深いため息を誘う。(下略)
(たかむら・かおる/作家)(構成・編集部)