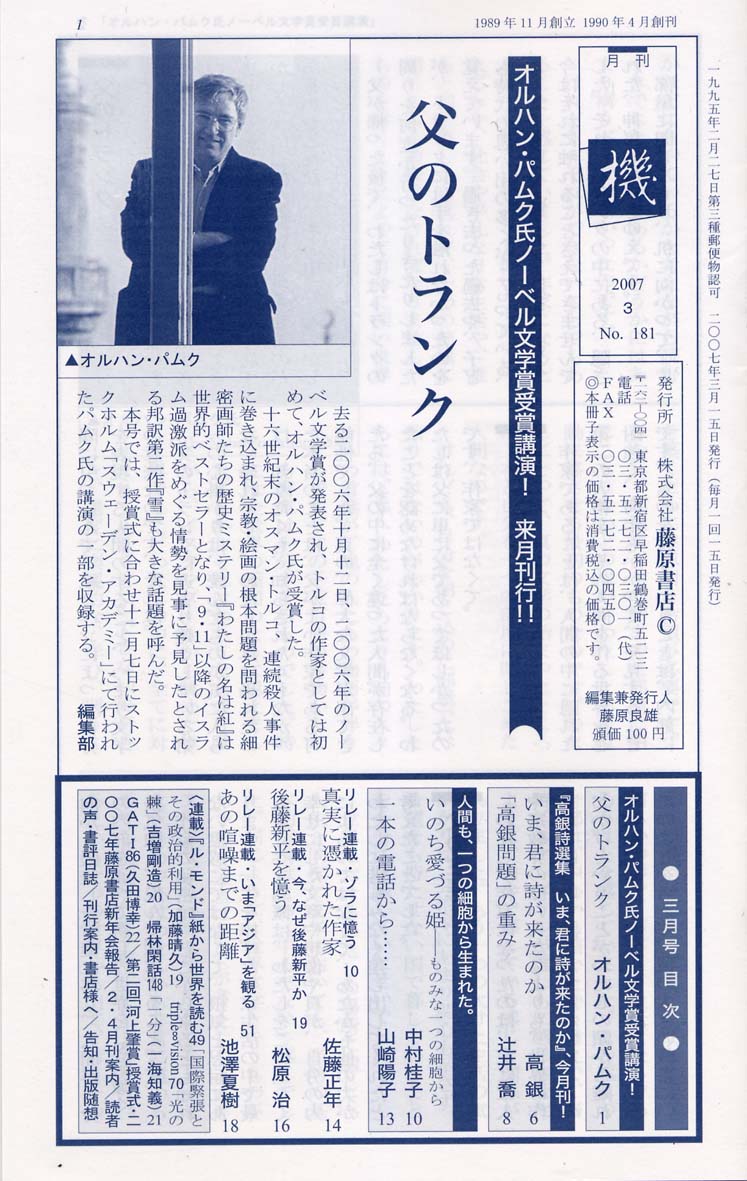真実に憑かれた作家──『文学論集』刊行にあたって
禁忌の糾弾
ゾラは、触れてはならぬものとしてそれまで文学から締めだされていた様々の素材を果敢に自分の作品に採り入れた。彼にとって人間の生にかかわるあらゆる現実は、それが読者の目にどれほど見苦しく残酷に映ろうとも見過ごすことの許されぬ真実に属し、当然文学の素材となる資格を有したのである。社会紛争、労働者、神経症に加えて、身体および性そのものも例外ではなかった。初期小説『テレーズ・ラカン』はすでに、若い女性の欲求不満と性欲をかつてないほど赤裸に描いているし、『マドレーヌ・フェラ』も生理学的な観点から見た酷たらしい性の宿命を語っている。
生物学的な意味での性を作品の中に組み込むことは、必ずしもゾラの創意になるものではない。それ以前にゴンクール兄弟が『ジェルミニー・ラセルトゥー』(1865)でヒステリーの生理学的な研究を行ない、その症状を医学の観点から記述していたのだから。けれども、ゾラの扱う性のドラマは単なる男女間の内輪の惨劇にとどまらない。それは後にもっと大がかりな変奏を加えられて、いわば交響化される。サイクル小説『ルーゴン=マッカール叢書』20巻は「第二帝政下における一家族の物語」であるが、生理学と遺伝学の観点から書かれた「自然史」であり、同時に「社会史」である。つまり、一つの同じ祖先から分岐したルーゴン、マッカール両家に属する人々の生物学的な歴史=物語と第二帝政の歴史=物語の両方をたどるのであって、一家族の病理は時代社会のそれと重なり合い、互いが互いを映し出す合わせ鏡となる。
ゾラが小説家の活動領域を実質的に拡大した生理学の名において力説するのは、性の解放、暴露、脱抑圧である。それは、身体からヴェールをはぎ取ってその中に入りこみ、そこに潜む様々な衝動や欲望、快楽、障害および狂気、すなわちリビドーを露わな姿で暴き出す創作態度を意味する。彼のペンのもとにしばしば現れる「人獣」(bete humaine)は、この理論的要請を一語にして要約している。自然主義の小説家は、人間存在にかかわるすべての事象を観察・分析し、粉飾を施さずに描かなければならない。人間が理性によっては抑制できぬ獣性の分け前を原初的な本能の中に秘めているならば、それを描くことがなぜ禁じられねばならないのか、これがゾラの根本的な問いかけなのである。
この肉体の自然化は、アカデミックな文学規範に固執する批評家たちを当惑させ、憤慨させずにはおかなかった。ゾラは新たな作品を出すたびに「不道徳」とか「猥褻」といった非難を浴びせられ、風刺画家たちからはゴミ箱を漁る屑屋になぞらえられたり、頭から室内便器をかぶった姿で描かれたのである。
科学主義と文学論
文学理論を構築する時に彼が参照するのはとりわけ自然科学であるが、なるほど今日から見れば至る所で論理に綻びがあることは否定できまい。その意味ではゾラは、科学的進歩の行き着く先に人類の幸福が約束されていると考える時代幻想の犠牲者と見ることもできるだろう。けれども彼の新しさは、文学の自立性を否定し、文学と科学を近づけ、文学活動を科学のそれに付随する、あるいは等質の営みとした点にある。彼によれば、小説家は自然科学者と連帯して、知の探求と普及という社会的な大事業に取り組まなければならない。だからこそゾラは、文学論で新しい文学の美学的な性質にとどまらず、文学者の果たすべき役割を強調する。
ゾラは真実という概念に憑かれた作家である。理論の上で彼の夢みる小説家とは、偽善的なプロテスタンティズムに染まった読者大衆に、真実を、つまりありのまま事実を語り、教育する作家を意味した。だからこそ彼は、様々な禁忌の封印を解き、その受容態勢をまだ十分に整えていない読者の目の前に、それを生の姿でさらけ出したと考えられるのである。
(さとう・まさとし/熊本学園大学助教授)