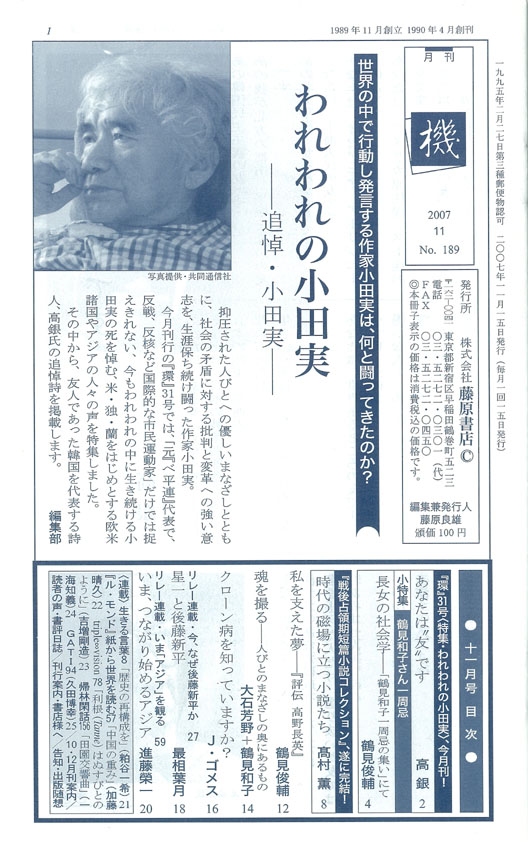この人の学問は全体として、長女の社会学だったと思います。
40歳をこえて米国に再渡米し、米国の社会学をまなび、プリンストン大学で社会学の博士になります。この時代には、彼女の師事したマリアン・リーヴィー教授の学風をふくめて、書く主体である自分を、論文の中ではふせます。彼女の場合、書く、そして考える主体である自分が長女であることは、伏せられています。
長女としての役割
4歳年下の弟から見て、この人は常に、4人姉弟の長女としての役割を演じていました。私の母は、私がうまれたばかりのころから私をなぐり、けり、柱や立ち木にしばりつけました。姉は、母のふるまいに異議を申したて、母の折檻にわって入りました。ともに米国に留学してからも、その態度は消えることがなく、1942年3月、私が連邦警察にとらえられて、私が東ボストン米国移民局に監禁されたとき、彼女は、当時敵性外人に必要な旅行許可をもらってケムブリッジの私の屋根裏部屋まで来て、都留重人夫妻、山本素明とともに、部屋に散乱している荷物を片づけてくれました。留置場まで会いに来て、私が書きかけの卒業論文をとられて手ぶらでとじこめられたのを知ると、あとで論文を大学がとりもどしてくれたのを受けて、書きついだ分を彼女がうけとってタイピストにわたし、大学におくる手だてをつくってくれました。そのため、私は、牢獄の中でハーヴァード大学を卒業することができました。彼女から来た手紙で、つかれたタイピストの肩をもんでやったことなどが書いてあって、そのことは、今も心にのこっています。
後見の眼の中にある社会学
1945年8月、戦争が終ると、彼女は、日米交換船以来、まる2年のあいだ、日本の論壇を見ていて、戦争万歳を書かなかった数人をあげて私にあたえ、その人びとを同人として雑誌を出すことを私にすすめました。
米国にいた間、彼女はマルクス主義者になり、日本にもどってからの戦中2年、その見方をかえませんでした。
私の父は、長女と長男を警察にわたすことはしませんでした。
私の父は、長女に、うまれた時から、大へんな肩入れでした。この無償の愛に、和子は、みずからの無償の愛をもってこたえ、父が倒れてからの足かけ15 年、父は失語症をかかえたままくらしました。その間彼女は、父の家を売って安い土地に移転し、その落差で父を支えました。すきぎれするときには、自分の教授としての給料と講演の謝礼、文筆収入をもってつなぎました。父をその最後までみとって、父にこたえたことは、彼女に平安をもたらし、彼女自身をその終りまで支えました。
父は、自分のこどもが、日本文化に根をもたない国際人になることを恐れて、彼女が8歳のときから日本舞踊をならわせました。その身ごなしは、彼女が脳出血に倒れ、上田敏、大川弥生両医師の開発した独自の回生の方法によって、ふたたび歩きはじめる時の重心の移動、半身不随のままの朝飯の調理、りんごの皮むき、片手を文鎮として原稿用紙をおさえての執筆に役立ちました。また、彼女は、健康なときにおこなった水俣病の調査を、半身不随となった患者として受けとめる新しい社会学の視点を得ました。
岩波ホールの舞台にたったとき、彼女は踊りのなかばで扇をおとしました。彼女は、たじろがず、そのままそこに立っていた。すると、後見が、立って彼女に、自分の扇をわたした。見ている丸山眞男は、そのとき少しもさわがずに立っている和子に感心したが、私は、後見の眼の中にあるそれまでに見てきた何千人ものおどり姿の中に社会学があると感じた。和子の社会学は、同時代という同じ舞台にたつ後見の眼の中にある社会学にむかって動いていた。
歌と社会学
父は和子にすすめて、津田英学塾にかよう彼女に、佐佐木信綱に入門して和歌をならうようにした。そこで彼女は、アメリカ留学を前に『虹』という歌集を出した。その後、半世紀、歌をつくらなかった。彼女にとって、和歌と学問とは別のものだった。だが、歌は彼女を捨てなかった。八十歳に近く、彼女が脳出血で倒れたとき、歌は彼女にもどって来た。はじめは型はずれだったけれど、だんだんに型がととのって来て、その後、彼女は、紀貫之の歌の理論、歌は、生きとし生けるものの、生きる姿勢の中にあるという伝統にもどりました。歌と社会学とは別のものではない。彼女は老人施設の中で、これまでの社会学論文を読みなおして、あとがきを書き、これまでの自分の学問に、自分の生命のいぶきをこめた。このようにして老人施設の中で、自分の著作集を出すことを完結しました。
(つるみ・しゅんすけ/哲学者)