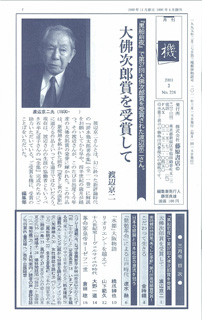リオリエント的批判のアイロニー
資本主義の起源はどこにあるのか。これは古い問いである。
この問いに対する古典的な答えは二つあった。ひとつは産業革命と結びついた「自由な賃労働」に資本主義の本質的指標を見出すもの。いまひとつは大航海時代に始まった「低開発の発展」に資本主義の本質を見出すものである。いうまでもなく前者は十八世紀後半、後者は十五世紀末に資本主義の起点を置く。
この二つの立場の対抗関係を背景におくと、世界システム論は前者のパラダイムを後者の立場から批判する対抗理論として一九七〇年代に登場したものである。
これに対して、A・G・フランクの『リオリエント』に代表される、一九九〇年代以降の世界システム論批判には、前者の側からのバックラッシュの側面がある。「十九世紀に至るまで人類史の大半を通じてグローバル経済の重心はアジアにあった」という彼らの主張は、「では十九世紀以降のヨーロッパによる世界支配はどのようにして可能になったのか」という問いを前景化し、産業革命期のヨーロッパ社会の変化へ関心を誘うからである。
だが超長期的な定常性に立論することが、かえって短期的な変化を強調する結果を招くのは、リオリエント的批判の最大のアイロニーでもある。
実際この点はヨーロッパ中心主義批判の立場に立つ歴史観のアキレス腱となっており、十八世紀までの近世における非ヨーロッパ世界の経済発展を強調する議論は、特に経済史の領域で近年守勢に立たされている。
ウォーラーステインの継承者
では世界システム論をより長期的な視座に開くリオリエント的批判は袋小路に入ってしまったのであろうか。この、いわばポスト・リオリエント的な問題意識に立つ研究の潮流は緒に就いたばかりであり、まだ明確な輪郭をとっていない。しかしその中から現れた有力なひとつの作品がエリック・ミランの『資本主義の起源と「西洋の勃興」』である。一見古色蒼然たるタイトルだが、「西洋の勃興」に付されたカギカッコが、そこから一周してきた問題意識を示している。
ミランの主張はある意味では単純である。すなわち、資本主義の起源は中世後期のヨーロッパにおける都市国家間システムにあるというのが彼の結論だ。だが都市そのものではなく、複数の都市国家がつくるシステムに照準しているところに注意されたい。競争的な都市間関係を条件として都市の商業エリートが政治的権力を持つようになったことが資本主義の制度的基盤となったというのである。
しかしなにより特筆すべき彼のアプローチの特長は、中世後期のヨーロッパを同時代の中国、インド、北アフリカの政治経済システムとの広範な比較にひらいたことである。彼は、静態的に生産性や生活水準を比較するのではなく、資本主義的成長を可能にする制度の発展のほうに軸足を置く。これはたとえばゲーム理論を駆使するアヴナー・グライフのような新制度学派と(政治的な立場こそ違え)共通の着眼であり、また彼の議論のポスト・リオリエント的たるゆえんでもある。
思えばウォーラーステインは長い十六世紀のヨーロッパを、ロシアとオスマン帝国から切断することで近代世界システムを括りだしてきた。それを「概念の実体視だ」と、フランクのようにまるごと拒否するのではなく、もう一回り大きな時空をとってもう一度比較に開いてみようというのがミランの姿勢である。その比較の流儀にはかつてのウォーラーステインの手つきが息づいている。同書を繙かれた読者は、『近代世界システム』を彷彿とさせるその筆致にウォーラーステインの正統の(批判的)継承者を見るだろう。
(やました・のりひさ/立命館大学教授)