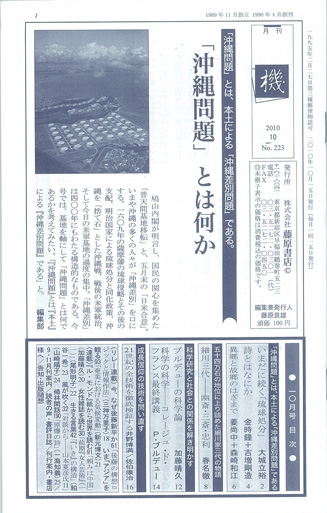「科学の科学」の意味
「科学の科学」というのはあまり見慣れない表現であるが、普通に使われている「科学哲学」「科学史」「科学社会学」「科学認識論」のことを言っているのだと割り切ることもできるし、それをあえて「科学の科学」と言ったところにブルデューの独自性の主張を見てとることもできるであろう。
「科学」というといわゆる自然科学、理系の学問と考えやすいが、また、自然科学的認識と人文社会科学的認識とは質的に異なるものとする立場があるが、ブルデューはこの両者を区別しない。同質のものと考えている。ブルデューが「科学」「科学的認識」「科学的事実」「科学的真理」と言うとき、数学・物理学・化学・生物学などいわゆる自然科学と同時に歴史学・社会学・経済学などいわゆる人文社会科学をふくめて論じているのである。この点をまずおさえておく必要がある。
『パスカル的省察』(一九九七年)において、それまでの経験的研究を総括して自分の人間論、社会論の集大成を試みたあと、コレージュ・ド・フランスでの最終講義を「科学の科学」にあてたのは自然な流れであったし、それはまた、科学論において決定的な足跡を残しておこうというブルデューの野心と意気込みの表現でもあった。
躍動する生身の人間
そうした材料によって、歴史を細部から眺めることができた。二人の敵をあしらいかねている主人の危機に、薙刀を手渡そうと庭に飛び降りる坊主、本能寺の変を知らせるため六四キロの道を六時間で駆け抜けて、泥足のまま城の広間に飛び上がる速足の浪人者、将軍暗殺の危機にあたって、やむなく置き捨てられた忠興を連れて、後日の証拠になるようにと、守り札と脇差だけを持ち、三年ものあいだ京都の裏町に潜伏した乳母……こうした無名の人々、ある場合には特異な能力をもつ個人が、歴史の転換点で一度だけ能力を発揮して、また闇に没してしまう。そのような人々の存在が物語を活気づけてくれるのである。
それほど女性が重んじられた時代ではないが、ここに現れる女性たちは機転がきき、颯爽としていてそれぞれに個性を発揮している。忠興の妹の伊也という人は、政略結婚であったにもせよ、夫となった人を兄忠興に謀殺されたことを憤って懐剣で切り付け、このため忠興の鼻のあたりには終生、その痕が残っていたそうである。
著名人もまた生身の存在として現れる。将軍と仲たがいしてさっさと岐阜へ帰ってしまう信長、それに狼狽して綿々と翻意するよう手紙を書く天皇、大名になれて上機嫌な幽斎、自分で気さくに膳を運びだして客を心服させてしまう信長、侘びた茶室で客に茶を点ずる秀吉、将軍の面前でわざと耳の不自由を装う忠興、忠興に愛児を抱かせて、物陰からそっと様子をうかがっている将軍家光……そういう人々の営みの総体が歴史を作ったのである。
強い圧力にさらされる科学
日本の場合、科学史・科学哲学や科学社会学の専門家ばかりでなく、科学研究に、現にいま、直接、たずさわっている人々、とりわけ物理学、化学、地球宇宙科学、工学、生物学、医学、薬学、農学など、いわゆる自然科学の専門家の人々に読んでいただきたいと強く願っている。科学研究の世界は相対的に閉鎖した自立的・自律的な世界であるわけだが、その世界が内部的にますます激烈な競争の世界であることはすべての研究者が知っている。研究費獲得競争、業績競争。それが昂じた挙げ句、データのねつ造をはじめとするスキャンダルが頻発している。また、科学研究の世界がこんにち外の社会からの強い圧力にさらされている世界であることも、すべての研究者が知っている。例を挙げるのは容易である。新型インフルエンザの汎流行(パンデミー)第六段階を決めた国連の世界保健機関緊急委員会委員長であるオーストラリアの微生物学者M教授はワクチンで莫大な利益を得たいくつかの大製薬会社と浅からぬ縁で結ばれていると伝えられている(Le Canard enchaine, 2010/02/03; Le Monde, 2010/04/16)。おなじく世界保健機関の専門家チームが七年かけて作成した研究・開発資金調達に関する報告書が公表前に製薬会社の国際組織の手に渡り、その結果、大製薬会社の利益に課税する案などが、いつのまにか、消えてしまっていた(Le Monde, 2010/03/27)。気候変動に関する政府間パネルの指導的研究者たちに対する執拗な組織的中傷が続けられる一方で、地球温暖化防止対策の成立を阻止するためにエクソンなどアメリカの化石エネルギー産業が展開しているロビー活動とキャンペーンの支出は過去六年間で四〇〇%増加しているという(Le Monde, 2010/04/20)。
科学研究が営まれる空間がどのような構造をもち、どのように機能しているのか、また、その空間が社会とどのような関係をむすび、相互にどのように作用し合っているのかを、研究者自身が再帰的、反省的に問い続けることはいよいよ大切になっているのではないだろうか。(後略 構成・編集部)
(かとう・はるひさ/東京大学名誉教授)