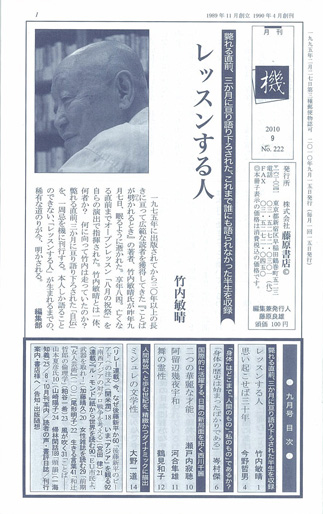茫洋として逃げ込んだ先
竹内演劇研究所に入ったのは一九七八年三月のことだった。役者やスタッフになろうとしたのではない。『ことばが劈ひらかれるとき』(思想の科学社/ちくま文庫)が出たばかりの竹内さんのところなら、演じることが、あらたな自分の発見につながるかもしれないと思ったのだ。消去される自分、ニュッと顔を出すまだ知らない自分、人前に晒される自分、そんな怖そうなものに賭けようと考えたのは、世の中に絶望し、先の見えない感覚にとらわれていたからだろうが、結果を言うと、あたらしい自分は発見できなかった。自分が更新されていく経験には、内実の深さや幅の広さにつながる一面があるが、固定的な存在証明(アイデンティティ)の書き換えになるわけではないからだ。(中略)
いま考えると、そういう私が、竹内さんのレッスンや舞台に求めたのは、自分を内側から根拠づけてくれる対象を、虚構でもいいからその都度あらたに見つけ出す作業だったと言える。レッスンや公演の場では、架空の話であっても、目の前にいる人とモノとに刺激を受けて動き出すイメージが、日常の予断を超え、考えもしなかった奔放な行動を呼び込むことがあるし、だからこそ思いもよらぬ自由な声とからだに出会う時がある。つまり、日常の自分を隠蔽する無意識の構造が、他者と交わす待ったなしのやり取りによって突然壊れ出すのだ。この体験は隠そうとしても隠せない強烈なもので――たとえば竹内さんは、「私が本当に私である時、すでに私は私ではない」(『待つしかない、か。』春風社、など)と言った――、その後、演劇から出版の世界に移り、主にインタビューすることを生業にしてからも、私の変わらぬモチーフの一つになった。竹内さんの近くにいた三年足らずの間に得た声やからだにかんする記憶を、オルゴールでも鳴らすように何度も確認し、相手が変わればその都度ねじを巻いて、同じテーマのバリエーションを聴こうとしたわけである。「何を」という情報収集ではなく、「なぜ」や「どのように」にこだわり続ける聴き手。そんなものがいまの時代に果たして成立するか。私の問いは、いつも竹内さんに立ち戻ることによって保たれてきたと言ってよい。(中略)
結論づけることと確かめること
インタビューには、情報収集ではないと言い募っても、文章という制度があるせいで、事実に内包する意味を抽象的にまとめ上げる傾向が抜きがたくある。対話であれ談話であれ、実際に話されたこととは異なる表現が頻発するこの矛盾を、『生きることのレッスン』(トランスビュー)で行った聞き書き原稿をチェックする際に、竹内さん本人からこう指摘されたことがある。「文章はわかりやすいし、よくまとまっている。でも、何かが違う」。私は答えた。「書いた後は、著者の直しを待つのがぼくの仕事です」。
その時のことをいったいどう言えばいいのだろう。ハンナ・アレントにならえば、「労働」や「仕事」に心を奪われていた私に対し、竹内さんは人間として「活動」し続けていたとでも言えばいいのか。その後、竹内さんは、私が献本した別の著者のインタビュー本の「あとがき」にあった私にかんするコメントを読み、こんな趣旨の葉書をくれた。「違うと感じた理由がわかったような気がします。あなたの文章は、彼が言うように簡潔で正確な要約だ。でも、僕は要約済みの結論を伝えようとしたことはないのです」。この竹内さんの自戒に、書くという行為の中で応えることができるか。私は、いつかその結論を出してみせなければいけないと思っている。
(こんの・てつお/編集者・ライター)