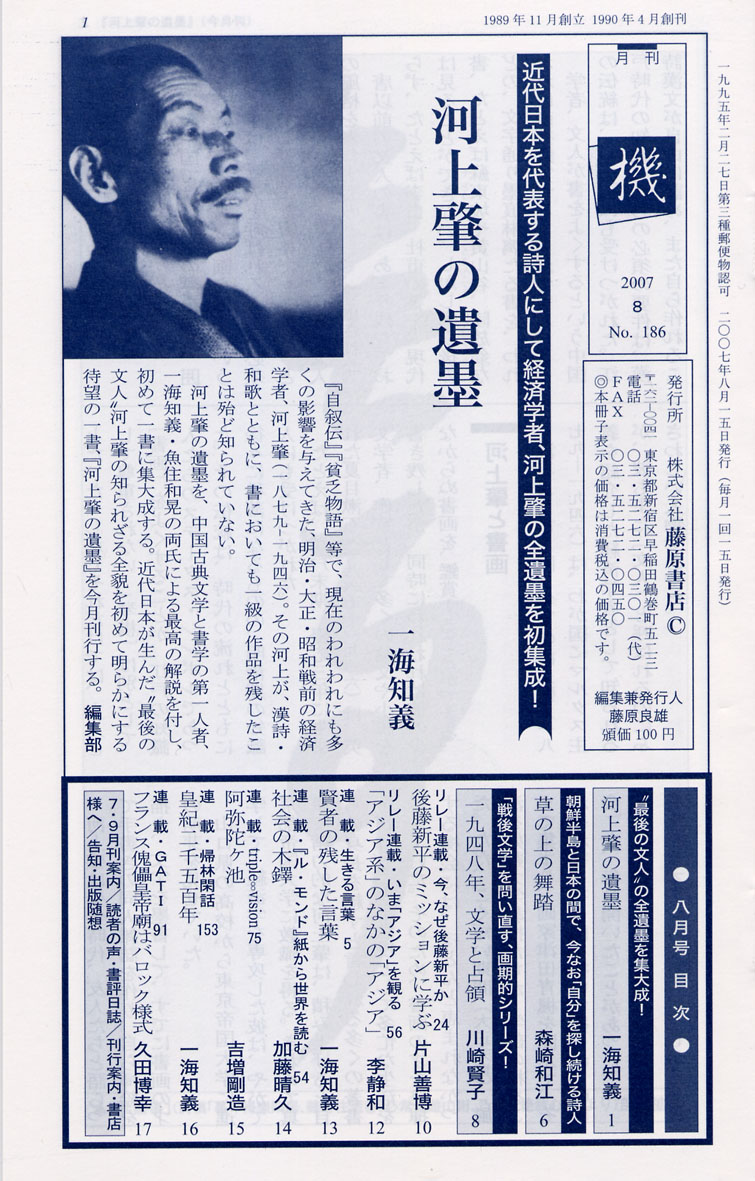一国主義に閉ざされた文学
1948年、GHQによるメディア検閲は、事前検閲からほぼ事後検閲へと移行し、検閲の方針も転換しつつあった。
1945年9月より開始したGHQによる検閲の流れは、棒ゲラに組んだ原稿を二部、CCD(民間検閲部)の所定のPPB(新聞・映画・放送部門)当局にさしだし、問題が無いか、あるいは一部削除、公表禁止などの指示を仰ぐというものだった。削除にあった場合には、誌面に空白、伏せ字などの検閲の証拠を見せない形に修正し、再提出することが義務づけられた。新聞・雑誌刊行まえの検閲すなわち事前検閲である。検閲される側には、削除、公表禁止などにあった場合に経済的な被害が生じる。検閲する側には、円滑な占領統治に必要な情報の統制、占領軍批判の抑制と、情報収集という利点があった。
検閲方針の転換には、国際関係の変化が影を落としている。敗戦直後には、戦争協力メディアに厳格に対処したが、連合軍内での米ソ対立および戦後の世界分割をにらんで、日本を西側に編入すべく、左翼の言説にたいする検閲が厳しくなる。この年、ドイツの東西分割はベルリン封鎖にいたり、イスラエル独立宣言と第一次中東戦争、8月に大韓民国樹立、大統領に李承晩就任、9月には朝鮮民主主義人民共和国が樹立、金日成が首相に就任した。中国共産党軍は、北京に無血入城する。東アジアの緊張は高まっていた。
いっぽうで外国雑誌の配給自由化がようやくGHQによって許可された。日本が国際ペンクラブに復帰した年でもある。占領、あるいは引揚げといった大規模な越境、移動のかげで、敗戦後の状況は、文芸の翻訳、国際交流に制限を加え、日本文学を一国主義の文学史空間のなかに閉ざされたものにしていたのだ。
太宰治の「あほらしい感じ」
戦場の死は遠ざかりつつあったといえるのだろうか。1948年の読書界を震撼させた最大の事件は、太宰治の情死である。6月の玉川上水に、太宰は山崎富栄と入水した。姿を消してから遺体があがるまで新聞報道は過熱するいっぽうであり、死にいたる経緯、行為の是非、太宰の文業の評価は、やがて雑誌に場を移して語り継がれた。専業の文学者だけではなく、官民問わずさまざまな職場の雑誌、地方誌や同人誌個人誌につどう素朴な書き手のあいだでも、太宰治の死と文学は議論の的となった。
本書には「家庭の幸福は諸悪の本」の警句で知られる「家庭の幸福」を収録する。「子供より親が大事、と思いたい」(「桜桃」)、「恥の多い生涯を送って来ました」(「人間失格」)など、規範からの脱落をことさら露悪的に語る太宰文学の魔に憑かれた読者も多かった。かつては太宰文学における政治性といえば、戦前の左翼運動との関係と挫折に焦点が当てられたものだが、占領期という視角から再読して興味深いのは「苦悩の年鑑」、「トカトントン」など、戦時イデオロギーにも占領期のイデオロギーにたいしても、ひとしくむなしさを表明する言説だろう。「時代は少しも変らないと思う。一種の、あほらしい感じである。こんなのを、馬の背中に狐が乗ってるみたいと言うのではなかろうか」(「苦悩の年鑑」冒頭)という姿勢である。その「あほらしい感じ」にはかろうじて持続的な批評の力がある。(後略)
(かわさき・けんこ/文芸評論家)