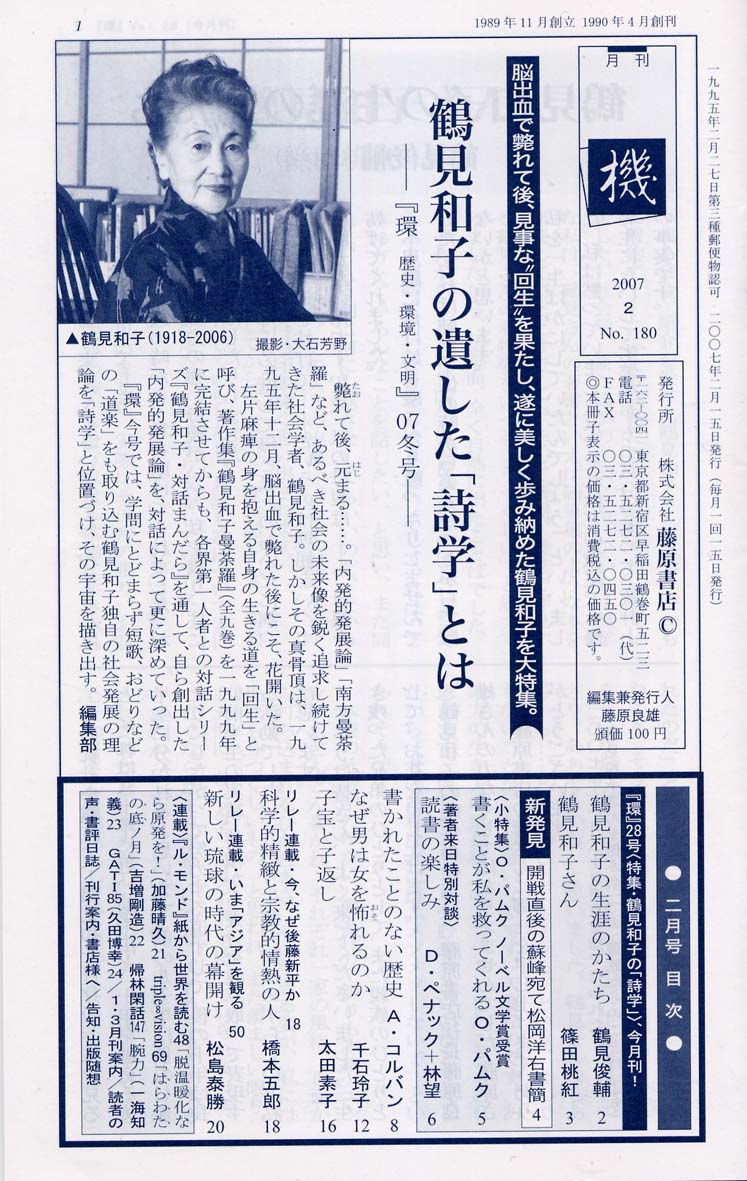●男と女の問題の根源に迫る!
「エッセイ」はしばしば随筆あるいは試論と訳されるが、その本質は思想の分析であり、エドワード・W・サイードの言葉を借りれば「機知と創意工夫と純然たる新奇さで人を驚かす」「根源的な遊戯性」をもつ。自由な発想が許されるジャンルである。
文学研究の呪縛から逃れているリピエッツ氏が創意と遊び心と機知によって『フェードル』を読み解いたこのエッセイは「根源的な遊戯性」に貫かれ、その「純然たる新奇さ」に驚かれる方もおられるだろう。氏の教養と興味の全て、シャンソン、映画、演劇、オペラ、美術、考古学、文学、哲学、精神分析が自在に援用され、こうして大胆に、易々と十七世紀文学世界の枠が越えられ、フェードルを現代が抱える問題の中で捉えなおしている。謙遜と矜持をまじえた日本的表現を借りて「独断と偏見」の書ではと思いたいところだが、ここに全くみられないのは「偏見」である。それを可能にしているのは、フランスの教育が技術優先の今にあってもなお最重要視する論考に磨き抜かれた氏の知性であろう。その元をたどれば、デカルトに遡る人間を人間たらしめている「知」への確信であり、錬磨であり、「知」による「偏見」の排除への果てることのない努力である。「偏見」を免れることがこのエッセイの始動力であり、リピエッツの知的情的人格である。
リピエッツの検証がむしろイポリットの罪を浮上させたことが私には興味深い。男性の女性への怖れがこれ程率直に分析されたことに感動を覚えた。この怖れが文明を作り、今さまざまな問題にさらされている。飼い慣らしたはずの〈自然〉にしっぺ返しを受けている。地球温暖化、少子化もその一つである。「なぜ男は女を怖れるのか」。自己と世界の喪失を怖れ、そして元も子もなくす。男性そして女性も「相対する性」にたいする怖れを除くこと、これが悲劇を増幅させない一歩ではなかろうか。
名声に輝く立派な夫を持った人妻の前にふと現れた義理の息子、清潔なエネルギーに溢れ、その面差しは夫に酷似しながら夫には失われた若さと高潔さに輝く。フェードルはこの義理の息子イポリットに恋してしまう。苦しみの末フェードルは恋を打ち明ける。夫は不在、生死も不明。しかし結果はイポリットの手ひどい拒絶であった。彼女は息子に辱めを受けたと、夫テゼーに逆の訴えをする。夫は当然怒りを爆発させ、真偽を確かめもせず息子を追放し死罪に処す。フェードルはこの成り行きに驚き、真実を告げて自殺する。世に伝わるフェードルの物語である。
しかしこれは殆ど十七世紀フランスの劇作家ラシーヌが描いた『フェードル』による。そもそもフェードルの物語はギリシャ伝説に端を発する。そして三人の天才、ギリシャ人のエウリピデス、ローマ人のセネカを経由してフランスのラシーヌによって真に悲劇的な作品に仕上げられたのである。
ラシーヌのフェードルが書かれた十七世紀は太陽王ルイ十四世の絶対王政下、ギリシャ・ローマを範として中庸と節度を追求し、真実らしさを重んじる古典主義時代である。イエズス会とポール・ロアイヤルをめぐり宗教論争が喧しい時代でもある。才気を振りまく女性たちが文学サロンに集った時代である。この時代を映す五作の『イポリット』が書かれた。ラシーヌはエウリピデスの健気で哀切きわまりないパイドラ〔フェードルのギリシア名〕の詩句をなぞり、セネカの恋に身を焦がすパエドラ〔フェードルのローマ名〕を加味しながら、抗いがたい恋の情念とその情念の根底に潜む“罪”を、いや、存在そのものが負う“罪”をみてしまうフェードルを、端整で美しい詩句から紡ぎ出した。
フェードル伝説にちりばめられた様々な罪、不倫の恋、近親相姦、嫉妬、讒訴、そして息子の罪、父の罪を全部取り込んだラシーヌのあらたな悲劇の様相は不思議な魅力を湛え、人々を悲劇の解明に駆り立てて止まない。しかし二十一世紀の私達にフェードルに課せられた罪の有効性が認められるだろうか。フェードルの悲劇とはいったい何なのか。
リピエッツの問題提起である。
フェードルに課せられた罪には実体がないことが二十世紀には気がつかれ始めていた。ロラン・バルトはフェードルは「唯名論」の悲劇であると。リピエッツは自ら彼女の再審を求める提訴人の名乗りをあげる。こうしてラシーヌの『フェードル』の、三百年前の“裁判調書”の再審がはじまる。
提訴人の証人としてはイリガライを筆頭として以下フェミニズムの理論家が名をつらねる。
検察はパリ・フロイト学派の精神分析思想家ラカンである。
提訴人は『薔薇の名前』の、謎の秘密文書の在処を求めて幾重にも巡らされた偽の道筋を辿ったバスカヴィルのウイリアムのように、“裁判調書”の偽の道筋を辿り、フェードルを断罪する秘密文書が「家父長制」であったことをつきとめる。しかし何故それが罪を作るのか。提訴人はこの“裁判調書”の原本であるエウリピデスの証言を掘り起こし、綿密にフェードルの台詞を検証し直す。フェードルの家系がたどられ、彼女の故郷クレタへ向かう。オリンポスの神々にはじまる膨大な家父長制の歴史のなかで懐柔されたディオニュソス神の存在が浮上し、世界を統治するために排除された循環的「性」と女性の「性」があぶりだされ、フロイトの「暗黒の大陸」から「迷宮」へ、ついに「罪の在処」、「女性のリビドー」に到達したかのように思われる。
リピエッツは神話に裏打ちされ、人々を魅了し続けるフェードルの告白を「女性のリビドー」を鍵に綿密に分析する、それは見事に。知的な分析と現代の慎みをかなぐり捨てた率直なことばによってイポリットと共に迷宮(胎)を辿る彼女の幻想のエロティックな様相が現れてくる。“ラシーヌは当時のプレシューズが語っていた“あのこと”をフェードルに言わせたのかもしれない〟。
ともあれ“ラシーヌはイポリットがフェードルを拒絶した世界を正直に報告した”。女性の欲望と敗北である。厳父ラカンは「女性というものは存在しない、女性は欲望のシニフィアンを持っていない。両性間の性的関係は存在しない」と。しかし根底にある男性の恐怖も報告している。迷宮的なディオニュソス的な女性の性への恐れ、自己と世界を支配する力を喪失する予感である。
フェードルは自らの罪、秩序を変えようとした勇気を罰し、独り深い闇の底へ落ちていく。そこでは地獄の審判である父ミノスが待ち受けている。一方忠実な〈父〉の息子イポリットは飼い慣らした愛馬に踏み殺される。〈父〉の法を守りすぎたから。フェードルとイポリットでは、「家父長制」の中にいる二人には異なってはいるがどちらも合法的な二種類の欲動、二種類の性による関係が不可能なのだ。
支配的性によって作られてきた文明は〈自然〉のなかにある相対する性を抑圧してきた。しかし〈自然〉を詐称する「不当な衣装」を身につけたものは懐柔したはずの〈自然〉に殺される。悲劇はこう警告しているのではないか。
悲劇は回避されるのだろうか。男性としてのリピエッツ氏の目は自ずとイポリットに向くようにみえる。“この〈父〉の息子は成人しても〈父〉にはならない。”新しい視点である。家父長制の衰退か。男も女もその“保護”から逃れ、自由をえるだろう。提訴人はこう呟く、“愛は悲劇そのものである”と。“他者の自由によって死ぬ刑”を覚悟しなければならないと。
この書は著者の含羞にみちたパートナーへの愛の書でもある。
(せんごく・れいこ/フランス文学)
2007年02月01日