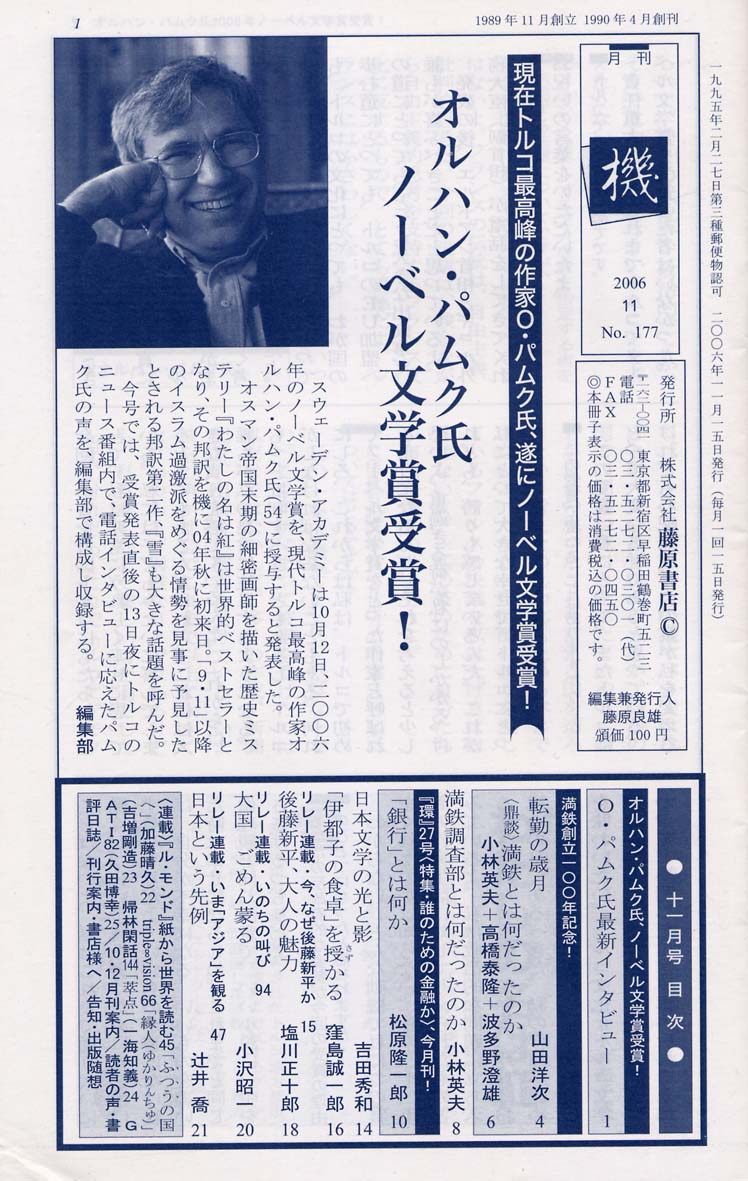●日本文学の核心に届く細やかな視線
バルバラ・吉田 =クラフト(1927-2003)の訳業で最も大きな部分を占めていたのは永井荷風で、彼の代表作『ぼく東綺譚』の翻訳には全力を傾けたし、それについで、これまで荷風で欠くことのできない著作『断腸亭日乗』の中から1937年という年を選んで、その全文を一字も剥さずドイツ語に移し変えるという作業には文字通り死力を尽して従事した。
元気で歩けるころは玉の井の事情に通じる人にお願いして、現地に赴き、懸命に調べられる限りは調べてもいた。女の人が生きるため、ああいう場所に生き、社会の中でほかに補いようのない仕事をしている人たちに対する共感をもったことも理由の一つではあったろうが。
彼女は心底からのナチ嫌いで、どんな時もヒトラーとその一味に票を投じたことのない両親を終生誇りにしていた。荷風の日記を読んでいても、そこに自分のナチ嫌悪に通じるものをみていたに違いない。『断腸亭日乗』で、日本が英米に宣戦布告した1941年12月8日の項に戦争のことが一行も出て来ない点には、大変強い感銘を受けていた。あすこには、銀座にいって友人と一緒に夕飯をとったとか、吉原にいって泊まったとか、そういうことは出てくるが、真珠湾攻撃のことには一行も費されていないのである。
同じことは戦争終結の日の項についても当てはまる。しかし、戦争が次第に深刻化する中で、まちを歩いていると、応召してゆく者とその家族をとりまいて、皆が旗をもって行進する有様とか、女の人たちの悲しい顔とか、こういうことはちゃんと書きとめている。
その反面、日本人はむしろ戦争になってから晴れ晴れとうれしそうな顔を見せるようになった、「日本人はどうやら戦争が好きらしい」という辛辣な指摘があったりもする。『ぼく東綺譚』とともに、こういう日記を書きつづけていた荷風にも、彼女は注目しないではいなかった。
彼女はこういう荷風の日記をどうしても訳したいと考えた。調べてみると、外国語にもいろいろな訳が出ている。しかし、それはすべて抄訳である。これではいけない。『断腸亭日乗』は一つの完全にまとまった文学作品としてコンセプトされている。構成においても、構文においても、どの細部も全体との関連の下に存在するよう構想されていて、「誰とかと飯を食べた」といった他人からみてどうでもいいようなことも、荷風にとっては、いつどこで誰と何をしたかというのは本当に大切なことだったのであって、それを省いてしまうのは、荷風を裏切ることになる、と彼女は考えた。そうかといって、あの大部の著作を翻訳するのは自分の手に余る。
こう考えた末、彼女は1937年という年をとりあげ、ここに出るものは一字も余さず訳すことにした。この1937年という年は、それまでは「事変」であって、日本本土から遠いところで大砲の打ち合いをやっているといった感じだったものが、次第に変わってきて、ついに真実身近かなものとして、庶民の生活に戦争の影が大きく射しかけてきた年である。
それに、1937年は荷風の最良の小説『ぼく東綺譚』の書かれた年でもあった。彼女は荷風がこの小説を書いたことと日本が本当の戦争に入ったこととの間には深い関係があると考えていた。
バルバラは2003年11月27日に死んだ。彼女は『断腸亭日乗』の1937年の項の翻訳、それから校正までは全部済ませた。あとは本として出るだけ。
私には、彼女がベッドの上で腹這いになって動けないまま、それでもなおペンを持つ腕を左右にふりながら仕事をしていた姿が、今でもまだ見える。
(よしだ・ひでかず/音楽評論家)