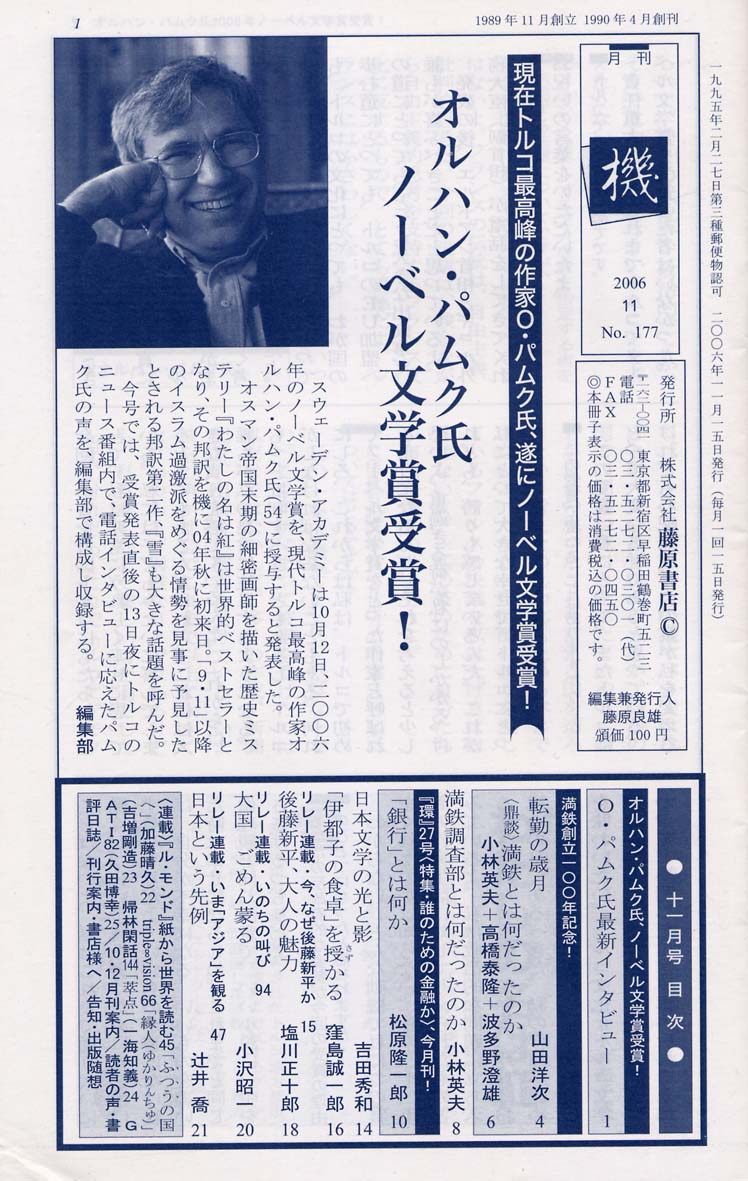企業と同時に誕生した金融
現在存在する「金融」は、「企業」の出現と同時に出現したものだと思います。
企業は、設備投資を行い、正社員を雇うため、事業の初めからある程度お金がかかってしまう。アイデアだけは持っている、しかし初期投資が必要というときに、こうした企業に融資する金融の役割が求められたわけです。とくに産業革命以降、起業家が出現し、経済の担い手、供給側の中心になる中で、金融のありようもかなり変質しました。
けれども、新商品については、どう市場評価されるのか金を貸す側も専門家ではないからよくわからない。ここに貸す側と借りる側の間にリスクの差が生じます。企業が新商品をつくるような場合は、その商品の評価はとくに難しい。こうしたところでいかにお金を貸したり借りたりするかが問題になります。
株式市場と銀行システムの違い
最終的に貸せる側と借りたい側がうまくマッチングすればよいのですが、このマッチングがなかなか難しいのです。戦後日本においては、基本的に銀行を中心にマッチングのためのシステムが組織化されました。証券市場もありましたが、それは銀行のシステムとは切り離されていた。
証券市場で株を発行してお金を調達する場合は、企業の抱えるリスクをすべて貸す側に押しつける恰好になる。最終的な貸し手がリスクを負担できるだけの情報力や分析力を所持していることが、株式市場が成立するための前提となります。だからこそヨーロッパでは、プロしか株式市場に入れない。そうした制限を外してしまったのがアメリカです。「自己責任」などと言って、全くわからないことについてギャンブルをさせて、失敗したらリスクを庶民に押しつける。
リスクの高い案件を処理するために専門家だけでやりとりをしようというのが、本来の株式市場です。ここにはお金の貸し手と借り手の間に立って調整するようなブローカーやリサーチャーが存在し、最終的な貸し手は、彼らからかなりの情報を得る。時に「インサイダー情報」に限りなく近いものだったりする。
金融自由化の帰結
これまで長い間、証券市場が特殊な空間として分離され、プロ以外は入れなかったのも、それだけこの手のギャンブルはリスクがあまりに高過ぎるからです。お金というのは、もう少しよく分かるものに対して貸すべきもので、こうしたギャンブルはまともなお金の運用ではないというモラルが、国民の側にも政府の側にも存在してきました。ですから証券市場は広く開放するようなものではないと、手数料なども高いまま放置されていた。一般の人々が証券市場に参加するようになった決定的なきっかけは、手数料が下がったということだったと思います。
こうした観点から見れば、現在のような金融市場の自由化は過剰と言うべきです。素人が参加すればするほど、儲ける人がいる。儲けるのは基本的にプロです。いち早く情報を得て、いち早く儲けて逃げる。全体として、情報を持たないような人が食い物にされるようなシステムになっている。プロは、企業について見誤らないのではなく、何よりも素人の投資家の行動に関して見誤らない。彼らは素人の投資家から儲けているのです。これまで長い間、証券市場が特殊な空間として分離され、プロ以外は入れなかったのも、それだけこの手のギャンブルはリスクがあまりに高過ぎるからです。お金というのは、もう少しよく分かるものに対して貸すべきもので、こうしたギャンブルはまともなお金の運用ではないというモラルが、国民の側にも政府の側にも存在してきました。ですから証券市場は広く開放するようなものではないと、手数料なども高いまま放置されていた。一般の人々が証券市場に参加するようになった決定的なきっかけは、手数料が下がったということだったと思います。
そうした株式市場以上に、これまで銀行システムの方が企業が置かれていた立場にある程度フィットしていたのは、企業自身もある程度リスクをとるべきだという意識があったからだと思われます。一般の人々から広く安定的に集めたお金を企業に貸す際、借り手の企業側も、自ら抱えるリスクをある程度「担保」という形で引き受け、固定的な金利をとられるのが、銀行というシステムなのです。
かしそうしたシステムがうまく機能したのは、それなりに経済成長率が高かった間で、現在のように成長率が低くなればうまく機能しないという問題も出てきます。全体として収益率が下がっているときに、借り手の企業が元々リスクを負っている上に、さらに「担保」までとられてやっていけるのかという問題です。そこで金融市場の自由化という議論が、借り手企業の負担を少しでも軽減しようという発想から出てきました。
そもそも金融業において収益率は、実際どの程度あるものなのか、あるべきなのか。特段優れた情報を持っていないとすれば、収益率は平均でしか分からないし、原理的にそれは経済全体の成長率と同じになるはずです。その意味で日本の株式市場は、トータルとしてはすでに儲からない構造になっている。儲かるのは、インドや中国など全体として成長しそうな国の市場です。日本国内の株で儲けようというのが土台無理な話である。
銀行改革のあり方の問題
何とか企業の負担を軽減しようと金融の自由化が進められてきたわけですが、それも現状では、全体の構図としては、本来、金融のプロがもう少しリスクを負うべきなのに、そうしたリスクを一般庶民が負わされる恰好になっている。そして銀行の方は、リスク負担や責任の所在が曖昧にされたまま、いつの間にか空前の収益を上げている。一般庶民からすれば、所持するお金を元に経済成長率くらいの収益は欲しいと考えるものでしょう。ところが貯蓄しても金利は低く、儲けようとすればリスクが相当かかる。それに比べて銀行はほとんどリスクを負っていない、それでいて担保をとっている、と頭に来てしまう。
結局、そういう銀行も行き詰まりを見せ、改革が不可避の課題となってきたのですが、その改革も、銀行にリスクを負わせる方向には向かわず、「金融の再編」や「大銀行の合併」で問題の解決が図られた。つまりこの間、大銀行は、経営や融資のあり方を自ら問い直すことなく、合併させられるかどうかだけを気にしてやってきた。不良債権問題も、公的資金の投入によって解決される。これでは、銀行は全くリスクを負わず、責任もとっていないのではないか、と一般庶民が不快感を覚えるのも当然でしょう。
金融機関は半ば公的な存在
では公的資金の導入は間違っていたかというと、そうではない。結果論から言えば、成功した。一銀行の倒産が全体としての金融危機につながる危険性があるからです。相互に連鎖するのが信用のメカニズムですから、そのメカニズムの全体をやはり何らかの形で守らざるを得なかった。
ではなぜ銀行は責任をとらないで済むのか。銀行の場合、一銀行の倒産が金融システム全体の問題になり得る。その意味で、金融機関は、本来からして半ば公的な存在であるのです。
(まつばら・りゅういちろう/東京大学教授)
※全文は『環』27号に掲載(構成・編集部)