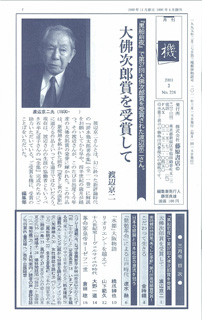十八世紀史について
ルイ十四世の死からフランス革命直前までを、ミシュレは十八世紀史の対象とする。この巻(『フランス史V』)では、その時代を扱う原書第十五巻(一八六三年)~第十七巻(一八六七年)の三冊から二一の章を抜粋する。
この中でミシュレが特に重視しているのは、ルイ十四世の死のあとに始まるオルレアン公による摂政時代(一七一五~二三年)である。太陽王の重圧がとれたという解放感からフランス中に自由の精神が広まり(カフェ)、経済改革が試みられるも失敗し(ジョン・ロー)、ペストが大流行したこの時期、フランス革命への道が見え始める。その後のルイ十五世、ルイ十六世の時代には野心に燃える政治家(ショワズール、テュルゴー)や女性たち(マリー・アントワネットら)の策謀が渦巻く。海のかなたアメリカの動向も絡みながら、自由と理性による検証をもとめる時代精神はますます高まり、絶対王政の足元が崩れてゆく。近づいてくる大破局の足音がミシュレの筆から伝わってくる。
フランス革命へ
ルイ十四世の死を語って十七世紀を閉じた『フランス史』第十四巻を、ミシュレは一八六二年二月に出したが、その直後、息子シャルルの死(同年四月)に遭遇する。しかし彼はくじけることなく、その年の大半を『魔女』および『フランス史』の続き(第一五巻「摂政時代」)の執筆に費やすだろう。前者は翌六三年二月、後者は同十月に刊行される。
同じく十八世紀を扱う第一六巻「ルイ十五世」と第一七巻「ルイ十五世とルイ十六世」も、それぞれ一八六六年と六七年に発表される。その間『人類の聖書』(六四年刊)の作成に時間をとられたりしたが、ミシュレは十八世紀の歴史に関し、その時代に刊行されたさまざまな書物のみならず、新聞雑誌類や、さらには未刊行の手稿類にもかなり目を通している。また最終巻では、ときおり、その時代を生きた人々の証言をも拾っているが、これは彼の歴史研究のひとつの特徴として、十九世紀当時としては特記されるべきことだろう。
ところで『フランス史』と銘うたれたシリーズの最終巻「ルイ十五世とルイ十六世」は、一七八九年四月の出来事までを述べて終わるのだが(本書最終章参照)以前彼が発表した『フランス革命史』(一八四七―五三年)は、一七八九年五月四日の「全国三部会」召集から語り始めているから、その直前までを描くことでミシュレはフランス史を、その起源から自らの誕生(一七九八年)前後の時期まで、ひとつの空白期もなく完結させたこととなるのである。
それゆえいわゆる『フランス史』の掉尾を飾る「十八世紀」の三つの巻は、何よりも「革命史」と結びつけることを目指して書かれたものといえる。したがって本書では、革命の誘因をあまた生み出したとミシュレが見る、ルイ十五世幼年期の「摂政時代」と、革命直前の混乱模様を活写した「ルイ十五世とルイ十六世」の二巻を中心に訳出した。結果として中間期(ポンパドゥール夫人やルイ十五世の娘たちが力を振るった時期)の紹介は軽く流す形になったが、フランス革命を歴史における一つの頂点と考える彼の歴史観を、限られた紙数内で紹介するための、やむをえない措置であるとして、ご容赦いただきたい。
(おおの・かずみち/中央大学教授)