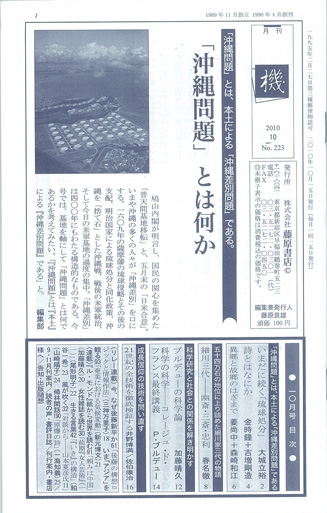歴史は人間の営みの総体
『細川三代』という作品で、この一族の歴史をおよそ百年にわたる持続と発展という角度から描いてみた。
百年、とはいうものの、出来上がってから数えてみたら、いつの間にか百年になっていたまでで、おもな関心は、細川一族の継続、発展の過程そのものにあった。
幽斎(一五三四―一六一〇)は足利将軍家に近い存在だったが、中世から近世へと人間のあり方も社会の価値観も大きく変わる時代の流れに身を置いて、同世代人である織田信長を選択し、丹後十二万石の大名になった。彼は一流の教養人でもあるとともに充分に政治的な存在でもあり、晩年には関ヶ原合戦のときに田辺城(舞鶴)で一万五千の敵に囲まれて籠城二か月、ついに古今伝授という歌学の伝統が絶えることを惜しんだ天皇の命令で名誉の開城を行う、というパーフォーマンスを演じてみせる。
子の三斎忠興(一五六三―一六四五)は豊前豊後で三十万石の大名となる。直情径行型の武人だったが、利休の弟子として茶でも名をなした。また徳川家康、秀忠、家光の政権に仕えるなかで次第に熟達した政治家へと変貌していった。
忠興の教育を受け、幕府に信頼された子の忠利(一五八六―一六四一)は、ついに肥後五十四万石の大名にまで上りつめる。
時代は下剋上とか、戦国大名の興起とか、織田・豊臣政権の成立とか、徳川幕府の確立と鎖国の完成とかいわれる時期にあたるが、そういう概念は整理の便宜上、後世の史家が考えたものにすぎない。
歴史を書く場合に間違いやすいのは、あらかじめ観念をもって歴史を組み立ててしまうことである。書き手が自分のなかに持っている《あるべき姿》ないしは《かくあって欲しかった歴史像》にあわせて歴史を書くことである。結果は明快にみえるかもしれないが、書き手も読者も得るものは自己満足だけ、という結果になる。
現実に起きたことは、そういう思い込みの歴史の想像をはるかに超えている。歴史というものが、さまざまの人間の営みの総体である以上、むしろそれを叙事詩のように語りたいと考えた。
「われ人とその勲いさおを語らん」(『アエネーイス』)である。つまり時間を経たて糸いとに、人と事件を緯あや糸いとにしてタペストリーを織りあげてみたかったのである。
それが可能だったのは、この時代には多くの日記や手紙が書かれ、とりわけ、対象とした当の細川家には連綿と手紙を書く伝統があったためである。
初代の幽斎は自分あての手紙を几帳面に保存した。三斎忠興は生涯にわたって、子の忠利に手紙を書き、忠利もまたこの習慣を受け継いだ。いまに残る忠興の手紙は二千通弱、忠利の諸方面にあてた手紙は発表されているだけで四千通を越える。
手紙を書くという行為そのものが、自己を見つめなおすと共に、相手を確認する行為である。細川家の政治学それ自体が、これらの手紙に支えられて成立したとすらいえる。また一方では、次第に《個》というものを重んずる時代が、このような場に反映しているとも見える。
躍動する生身の人間
そうした材料によって、歴史を細部から眺めることができた。二人の敵をあしらいかねている主人の危機に、薙刀を手渡そうと庭に飛び降りる坊主、本能寺の変を知らせるため六四キロの道を六時間で駆け抜けて、泥足のまま城の広間に飛び上がる速足の浪人者、将軍暗殺の危機にあたって、やむなく置き捨てられた忠興を連れて、後日の証拠になるようにと、守り札と脇差だけを持ち、三年ものあいだ京都の裏町に潜伏した乳母……こうした無名の人々、ある場合には特異な能力をもつ個人が、歴史の転換点で一度だけ能力を発揮して、また闇に没してしまう。そのような人々の存在が物語を活気づけてくれるのである。
それほど女性が重んじられた時代ではないが、ここに現れる女性たちは機転がきき、颯爽としていてそれぞれに個性を発揮している。忠興の妹の伊也という人は、政略結婚であったにもせよ、夫となった人を兄忠興に謀殺されたことを憤って懐剣で切り付け、このため忠興の鼻のあたりには終生、その痕が残っていたそうである。
著名人もまた生身の存在として現れる。将軍と仲たがいしてさっさと岐阜へ帰ってしまう信長、それに狼狽して綿々と翻意するよう手紙を書く天皇、大名になれて上機嫌な幽斎、自分で気さくに膳を運びだして客を心服させてしまう信長、侘びた茶室で客に茶を点ずる秀吉、将軍の面前でわざと耳の不自由を装う忠興、忠興に愛児を抱かせて、物陰からそっと様子をうかがっている将軍家光……そういう人々の営みの総体が歴史を作ったのである。
パレードとしての歴史
さきにタペストリーを織るように、と書いたが、わたしにとって歴史は、無限に連なる祭典のパレードだ、という絵画的なイメージがある。対象とした時代が、絵画資料に豊富であることも、こうしたイメージを想起する。
この時代には、肖像画や合戦図屏風、南蛮人屏風、洛中洛外図に江戸図と風俗画が多く描かれた。
追善とか称徳とかの目的があるにもせよ、肖像画が多いのは、やはり個というものが意識されるようになり始めた時代風潮によるのだろうか。沈鬱ともいえる表情を浮かべる織田信長、華やかに装っているが、かえって老いの醜さ、無残さをつきつけてみせる「醍醐花見図屏風」の豊臣秀吉、三方ヶ原の敗戦を自戒するために描かせたと伝える、うろたえた表情の徳川家康……。
歴史的な事件についても、鉄砲の集団使用で名高い長篠合戦、家康の野戦での強さをみせつけた長久手合戦、天下分け目の関ヶ原合戦、豊臣家の滅亡を彩る大坂夏の陣など、躍動する男女の姿が大きな構想のもとに色鮮やかに描かれている。
これらの戦争画における群衆処理はいくらか類型的だが、「洛中洛外図屏風」にみられる華やかな祇園祭の情景、「豊国祭礼図屏風」で踊る人々の熱狂、「江戸図屏風」にみられる日本橋界隈のにぎわいなど、次第に庶民生活にまで画家の目が及ぶようになることが、時代の動きを感じさせる。
さいわい細川家の主人公たちの肖像画も残されていて、幽斎とその夫人麝香(光壽院)(一五四四―一六一八)の対になった肖像は日本における夫婦の絵として傑作だと思う。文武に優れていた幽斎の表情は福々しく、いかにも闊達である。夫人のほうは、気ままな夫を優しく見つめている風情がある。この夫妻の仲は穏やかなものだったようで、当時としては珍しく側室の影もなかった。
茶人としても著名だったその子三斎忠興の晩年の肖像はいかにも神経質で気難しそうである。そして熊本藩主におさまったその子忠利の顔は、先祖たちの貴族的な容貌から一変して、あごの張った横長の顔となる。
さらに四代目にあたる光尚(一六一九―一六四九)は三十一歳で早世したので、いかにも若く、わがままそうである。江戸育ちのこの青年は、藩主の座を継いだとき、戦国の気風を残す熊本の家臣団としっくりしなかった。それが森鷗外の『阿部一族』に一端が描かれている父忠利の家臣団の排除につながったという。
ついでながら「殉死」という観念にとらわれた『阿部一族』は、史実を正確には反映しておらず、悲劇の性格を歪めてしまった。これも歴史の恣意的解釈の例である。
「より人間的な」叙事詩
ギリシャ・ローマの叙事詩では、英雄といえども神々の意思のあやつり人形めいて描かれている。戦闘場面で突然、神が介入してきて、優勢だったはずの勇士が殺されたり、英雄が突然、道ならぬ恋におちたり。……これにくらべるなら、少なくとも細川三代の物語では、人間は自分の誇りや欲望、偉大さや卑小さにたいして責任をもった存在であるようにみえる。その意味ではこの叙事詩はより人間的である。
そのことが、いまここにあるわたしたちという存在を、どこか深い部分で鼓舞してくれることをひそかに願うのである。
京都の祇園祭の山鉾の飾りにホメーロスや旧約聖書に材をとった、ヨーロッパの十六世紀ごろのタペストリーが使われていることは、限りなく想像力を刺激するものがある。この文章の最初に引いた『アエネーイス』のタペストリーもたしか大津の山鉾で用いられているはずである。ローマの叙事詩の英雄が、日本の神々の飾りとなって、祭礼の熱狂のなかを運ばれて行く。歴史は無限につづく祭りの行列であるのか?
(はるな・あきら/作家)