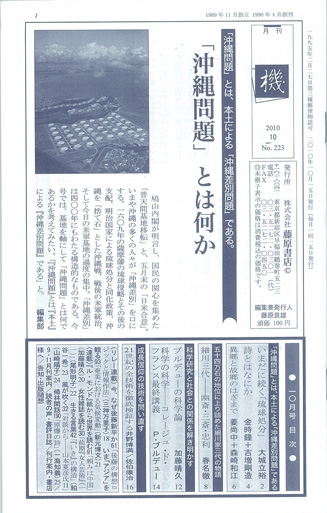侵略同様の併合
拙著に『小説 琉球処分』というのがあって、一九五九年からほぼ一年をかけて沖縄の新聞に連載し、単行本にもなったが、それほど売れなかった。それが今になって、急遽文庫本になって読まれることになった。
この事情が「沖縄問題とは何か」という問いへの答えにもなろうか、という気がする。琉球処分にはじまる近代沖縄の問題が、浮き沈みする運命を見るのである。
明治維新をなしとげた日本政府にとって、独立――清国と両属の琉球王国の存在は国防を不安にするものであった。それで八年間をかけて併合した(一八七九年)。処分という言葉を使ったのは、日本政府である。琉球側の抵抗を押して清国との交流を断たしめ、侵略同様に「日本」に併合する、その意味の言葉であった。
無理やり併合したものの、文化的にあるいは生活水準で日本人らしくないので、差別が生じ、県民の側では、それに我慢がならずに僻を生じ、他方でそれを超えて日本人らしくなるための同化が多くの県民の願いになった。
沖縄県民の同化志向にもかかわらず、戦争の末期に、軍部は米軍が本土に上陸するのを遅らせるために、沖縄島に釘付けにする戦略をとった。そのために沖縄県民がどれほど辛酸をなめるか、たぶん想像もせず、遠慮がなかった。軍人たちによる県民への差別も日常的におこなわれた。それでも、たとえば男女の中等学校生は必死に戦った。日本人として十分に認められたかったからに、他ならない。
この真情を、昭和天皇やサンフランシスコ平和条約での吉田茂は無視した。その結果、沖縄は半永久的にアメリカの占領下におかれ、そのおかげで、本土だけの日本は国防費の計上を免れて、高度成長をなしとげた。
払拭されない沖縄差別
沖縄では、まもなく「祖国復帰運動」が起きた。これはもと米軍支配から逃れたいためのことであったが、「独立」の方法をすでに忘れていたので、次善の策を望んだにすぎない。これをしかし、佐藤栄作は利用して、米軍基地温存の沖縄県を実現させた。
復帰運動のさなかにも、「祖国」を本能的に、あるいは無条件に求めたのではなく、「ヤマトぎらい」は腹の底にくすぶっていたのだが、それを表に出すことは、タブーのようになっていた。これを私は「沖縄の民衆は本土にたいする同化志向と異化志向の間で揺れている」と表現したが、この発言は「復帰」に水をさすものとして、歓迎されなかった。
本土に住むヤマトンチュたちは、この複雑な真情に想像が及ばず、「復帰」で沖縄を救い上げる、と認識していたようである。その認識のはたで政府は、思いやり予算による米軍基地の借地料をどんどん吊り上げることで、沖縄県民が基地を手放せないようにした。麻薬を押し付けるようなものであった。本土の基地を沖縄へ移すことさえも、厚顔に進められた。
それでいながら、復帰の前後に沖縄への財政投資について、国会議員のなかで「沖縄を甘やかすな」という声が出た。沖縄に甘えて基地負担を免れて高度成長に浴しているのは、どっちだ?と私たちは思った。さては、どの県で選ばれた議員であっただろうか。
歴史教科書に「沖縄戦での集団自決は軍命によるものだ」と書くことに、文部科学省が反対して、沖縄県民を怒らせた。これは、「史実を曲げるな」と批判したことになっているが、真意は「軍の名誉を擁護するというかたちで、琉球処分いらいの差別を、まだ保持しているのか」という不満である。
差別が払拭されないから、琉球処分がいつまでも思い出されることになる。
(後略 構成・編集部)
(おおしろ・たつひろ/小説家)
*全文は『環』43号に掲載。