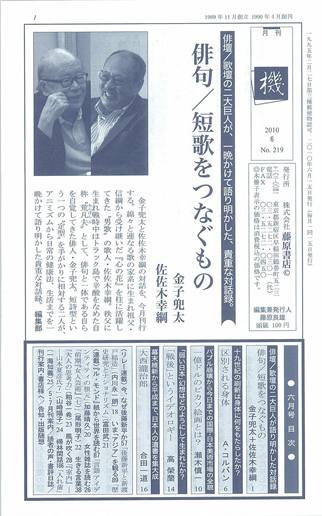日本の「八月」
一九九四年八月は、日本で過ごした初めての夏であった。未だに忘れられない衝撃を受けた暑い八月であった。六日は広島に、九日は長崎に原爆が落とされたこと、連合軍の大空襲、沖縄戦などについては歴史的知識として知っていた。しかし、それらの惨状がテレビ画面に映し出されるたび、「日本」で死んでいた人々に対する自分の想像力のなさに気づき、驚愕したことをよく覚えている。
韓国で蓄積された、戦争をめぐる私の記憶は間違いだったのだろうか? 日本のメディアをいくら眺めても、韓国の八月に召還されるような残虐な日本軍人は何処にもいない。戦争の悲惨を体験した「日本国民」の悲しみに満ちた声だけが聞こえる。その記憶を共有しない「他者」が入る隙間などないのである。広島にも長崎にも、東京にも沖縄にも、植民地から動員された人、移動してきた人が住んでいたはずである。そして、日本軍と殺し合いをした大陸や島々での「敵」、日本軍によって殺された民間人、「日本人」として戦った植民地の人々がいないのはおかしい。日本帝国は、無力な「我々」の頭の上に爆弾を落とすアメリカという大きな「敵」とだけ戦ったわけではないはずである。日本の「八月」にそれらがあまり前景化されないのは何故か。どこで何が捻れてしまったのか。本書は、その些細な疑問から始まったものである。
本書で扱うテクスト・出来事の配置は、日露戦争前後―アジア・太平洋戦争―占領期という流れになっているが、通史的手法をとってはいない。むしろ一九四五年から五五年までの間に近代の記憶がいかに再編され、それが日韓国交正常化、ベトナム戦争、冷戦崩壊、九・一一という言葉に遭遇することによって、どのような衝突と再編を繰り返したのかについて注目したものである。記憶は断絶されるものでも、継続されるものでもなく、歴史的・社会的コンテクストと交渉しながら再編を繰り返すものではないだろうか。
ノイズとしての戦後
「戦後」という言葉と交渉する過程で編成される歴史的記憶は、一九四五年から五二年まで続いたGHQ占領の記憶によって作られた、強いアメリカ対弱い日本(植民地・日本)という枠組みから自由だとは言いにくい。戦後あるいはイデオロギーという言葉と最も無縁に思える阿部和重の長編小説『シンセミア』(二〇〇三)すらも、九・一一以後に再編される占領の記憶、いわば「植民地・日本」という表象と補完関係におかれてしまう。「弱い日本」―「平和なニッポン」幻想はつねに旧植民地の記憶との抗争を繰り広げてきたのではないか。
本研究の狙いは、「戦後」のかわりに「ポスト・コロニアル」という枠組みから、日本の近代へアクセスするのではなく、むしろそれらの言説の交錯に注目することである。ポスト・コロニアルという言葉を媒介に過去の植民地支配の記憶が、「戦後」に新たなノイズとして作用しているのは確かである。冷戦崩壊以後、両方の言説が交錯する過程で生じた記憶の抗争がそれである。その過程で浮上してきたのが「抵抗」をめぐる言説であろう。
現在のナショナル・アイデンティティに基づく線引きによって出現する遠近法的構図を警戒しながら、近代における抵抗と連帯の言説が如何に編成されていたのかについて考えてみたい。それは、私自身が置かれている複雑な社会的コンテクストを相対化し、自分自身のアイデンティティがどのように構成されるのかを問い続ける作業にもなるだろう。
(コウ・ヨンラン/日本大学専任講師)