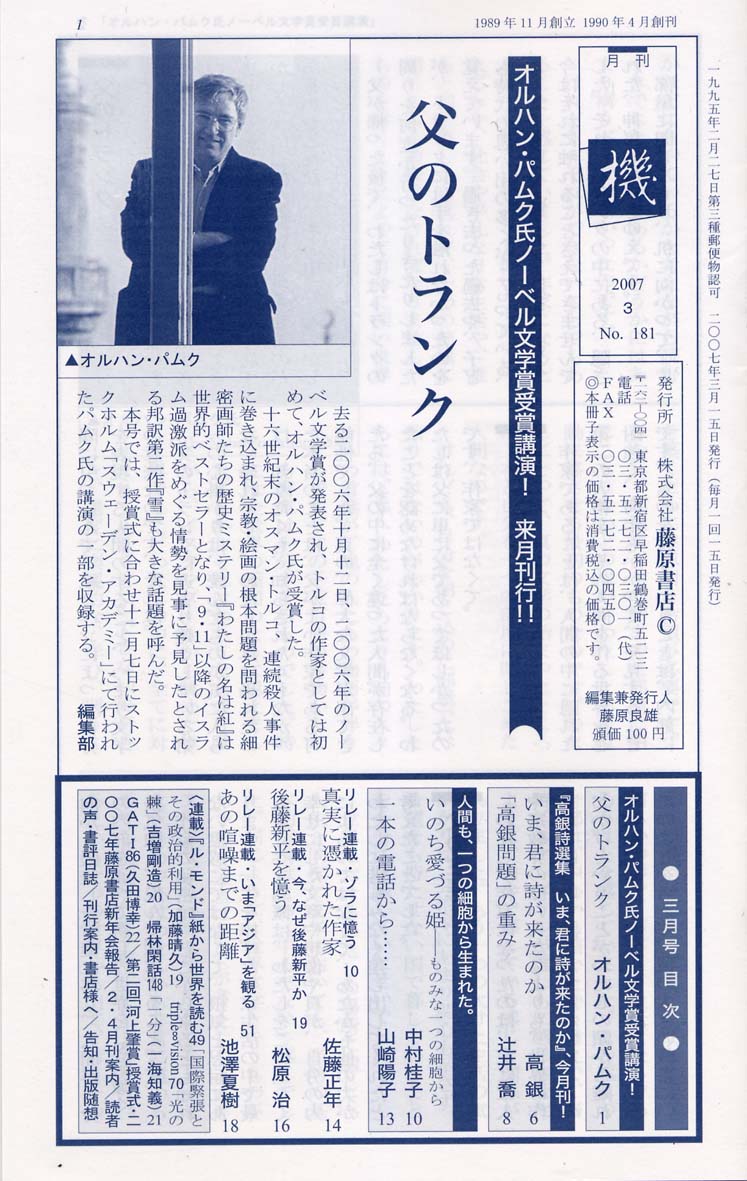細胞って?
「ものみな一つの細胞から」。生きもののことを考えるときの基本として、私が大事にしている言葉です。
細胞。最近は、DNA、ゲノム、遺伝子、さらにはタンパク質、糖など、生きものについて語るときに、さまざまな言葉が登場します。とくにDNAや遺伝子は人気があり、愛も戦争もすべてこれで語られています。
確かにDNAという物質は、おもしろい。調べれば調べるほど、生きものの特徴が見えてきて興味深いものです。でもDNAは物質であり、それが遺伝子としてはたらくには、細胞という場がなければなりません。DNAやタンパク質があるだけでは、「生きている」という状態にはなりません。ここがとても大事なところです。生きている最小単位は細胞です。だから、たった一個であっても、細胞であるバクテリアはれっきとした生きもの、大活躍です。
現代科学の方法で、細胞をつくることはできません。「細胞は細胞からしか生まれない」のです。でも、たった一度だけ、太古の海――化石などの証拠から38億年ほど前だろうとされているのですが――で、一個の原始細胞が誕生したことは確かです。これがなければ、今地球で暮らす生きものたちはどれも生まれてこなかったでしょう。もちろん私たちも。別の言葉で表現するなら、地球上の生きものはすべて、この細胞から生まれた仲間だということです。
「ものみな一つの細胞から」という言葉の中には、このように細胞の大切さ、私たち人間も含めて生きものはみな同じ仲間だということ、さらには私たち一人一人の存在の背景には38億年という長い歴史があることなど、生きもののもつ豊かな広がりに思いを致しましょう、という気持ちがこめられています。
「蟲愛づる姫君」との出会い
ある時、ある物語に出会いました。11世紀、『源氏物語』とほぼ同じ時期に書かれたとされている『堤中納言物語』の中の「蟲愛づる姫君」です。
平安の都に住む大納言の姫君は、小さな虫を小箱に入れ、「これが成らむさまを見む」「鳥毛虫の心深きさましたるこそ、心にくけれ」と言ってかわいがります。「人びとの、花、蝶やと愛づるこそ、はかなくあやしけれ。人は、まことあり。本地尋ねたるこそ、心ばへをかしけれ」。
「本地尋ねたる」は、仏教用語で「本質を問う」という意味だそうです。日本の物語のなかでこの言葉が用いられたのは、これが初めてとか。
侍女など周囲の人は、「そんな汚いものを」と逃げまわりますし、両親は、「これではお嫁に行けないのではないか」と心配します。けれどもこのお姫さまは動じません。先にあげた言葉で、みなに問いかけます。「毛虫をじっと見ていると、あなた方が美しいという蝶になるのです。あなた方は、花や蝶を美しいというけれど、これらははかないものでしょう。生きる本質は毛虫のほうにあり、時間をかけて見ているととても愛しくなる。これがわからないの」と。
卵から幼虫へ、さらに成虫へという変化を追うのは、発生生物学であり、しかも見かけにとらわれず本質を知ろうとするのが、本来の科学のありようです。ヨーロッパで近代科学が誕生したのは17世紀ですから、それより600年も前に、科学の精神をもったお姫さまが日本にいらしたというのは、なんともうれしいことです。
それにもう一つ、このお姫さま、「人は、すべて、つくろう所あるはわろし」と言って、当時上流階級の子女には当然とされていた、眉を抜いたり、お歯黒をつけたりということをしないのです。現代の言葉を使うなら、自然志向です。あるがままをよしとし、小さな生きものが懸命に生きる姿を見つめ、それを「愛づる」ことは、生きものを知る基本でしょう。
「生きている」って?
現代科学は、ガリレオ、デカルト以来、生きものも含めて、自然を数式で書かれているととらえ、機械として解明していくことによって進歩してきました。生命科学は生きものを機械をみなし、その構造と機能を解明すれば生きものがわかる、としています。しかし、38億年前に生まれ、これまで続いてきた生きものは、歴史の産物、つまり時間をつむぎ、物語を語り継いできたものなのです。生きものの中にある歴史を読みとり、生きていることを全体として、過程として捉えていかなければ、「生きている」ことを知ることはできません。このように考えている「生命誌」の原点は、まさにこのお姫さまにあります。
(なかむら・けいこ/JT生命誌研究館館長)
一本の電話から…… 山崎陽子
十数年前、月刊の小冊子に青春小説を連載していたころ、やはり連載されていたのが中村桂子先生の「科学といのち」シリーズでした。こんなにわかりやすく生命の神秘を説けるものかと感嘆し愛読していたその方から、ある日突然いただいた電話に、胸がときめきました。
童話や朗読ミュージカルなど、およそ科学には縁遠い世界にいる私に、なにをお望みなのか見当もつかないままお会いした先生は、いきなり38億年もさかのぼってのバクテリアの話から、ものみな総ての始まりが一個の細胞であることを熱っぽく語り、“彼ら”を登場させた「朗読ミュージカル」を創れないか、とおっしゃったのです。
『堤中納言物語』に出てくる「蟲愛づる姫君」と細胞たちの共演を、という先生のご要望をうかがって、グラリと心がゆれ、思わず身をのりだして口走っていました。
「姫君と出会うバクテリアは威勢のいい飛脚のいでたちでベランメエ口調、ミドリムシは京ことばの美女、なんていうのはいかがでしょう?」
乗りかかった船、なにはともあれ、さしたる知識もない私なので、まずは“細胞たちの主張”を教えてくださいとお願いして、失礼したのですが……。
数時間後、先生が帰途、新幹線のなかで書かれたというバクテリアの自己紹介が、FAXでとどきました。なんとそれは、めっぽうイキのいい江戸っ子バクテリアの主張だったのです。
なんてすてきな科学者! かくしてFAXが飛びかい、姫君と細胞一座による不思議な脚本が完成したのです。
(やまざき・ようこ/童話作家・ミュージカル脚本家)