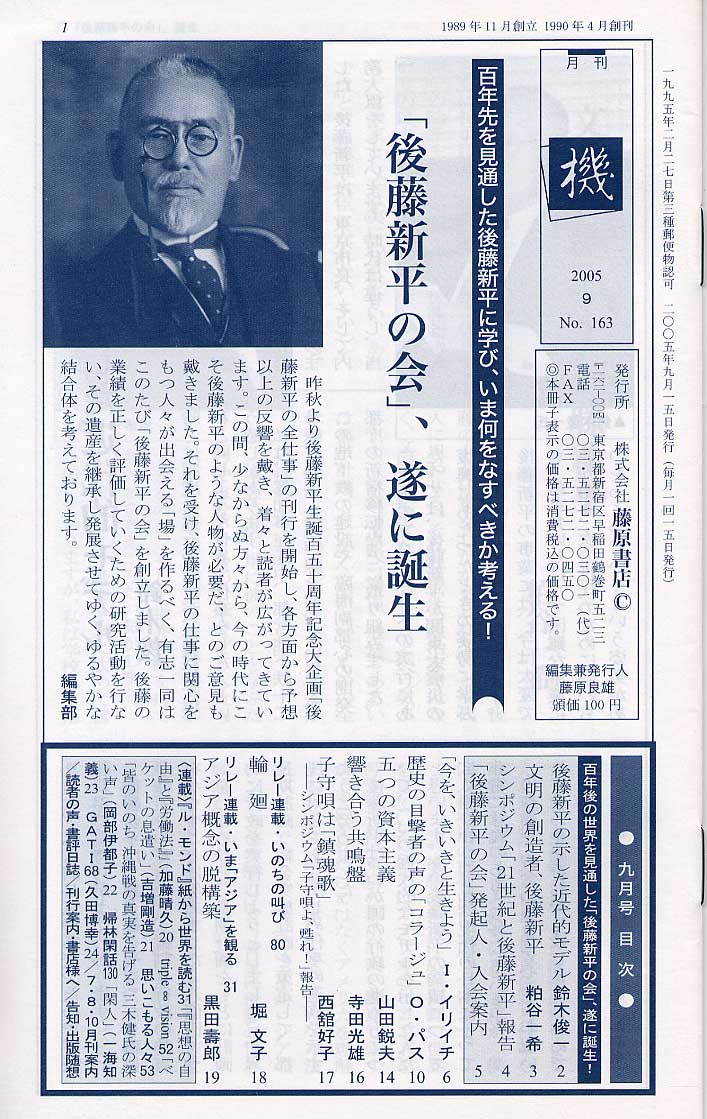歴史の目撃者が発した声の「コラージュ」
1968年の学生運動と、それを突如として終わらせた、政府による凄惨な弾圧は、メキシコの人びとを深く動揺させた。その結果生じた政治的、社会的、倫理的危機はいまだに解かれてはいない。エレナ・ポニアトウスカの『トラテロルコの夜』は、これらのできごとを解釈しようとしたのではない。理論あるいは仮説という類のものをはるかに越える何か、すなわち、筆者が呼ぶように「歴史の目撃者が発した声」の「コラージュ」なのである。一編の歴史記述――それも、歴史が凍りつき、生の言葉が文章化される前に、我々に歴史を示してくれるクロニクル〔スペイン語ではクロニカ〕である。
歴史記述家にとって、耳を傾ける術を弁えていることは、筆が立つことよりさらに重要なことですらある。こう表現するほうがよいかもしれない。書くことの技は、その内に、聴く技をすでに会得していることを含んでいる、と。それは、繊細にして至難の技である。なぜなら、鋭い耳を要するばかりか、偉大な倫理的感性、つまり他者の存在を認め、受容できるかどうかが問われるからである。作家には二通りある。自分自身の内なる声に耳を傾ける詩人と、周辺世界の数多の声つまり他者の声に耳を傾ける小説家、ジャーナリスト、歴史家と。エレナ・ポニアトウスカはまず、メキシコで最も優れたジャーナリストのひとりとして名を成した後、まもなく完璧なまでに劇的な短篇と、すぐれて独自性あふれる小説の書き手として広く迎え入れられた。彼女の描く世界は、突飛な諧謔精神と幻想によって支配されており、そこではごく普通の日常の現実と不気味で思いもよらない現実とを切り離している境界が曖昧でぼやけたものになる。本書の中で氏は、話を聴き、歴史を刻むために他者が語らなければならないことを再生するうえで、並外れた能力を発揮している。本書は歴史の物語であると同時に、きわめて想像力に富む、言語の妙技なのだ。
熱烈な証言録
本書は熱烈な証言録である。しかし、一方に傾いたものではない。熱烈であるのは、不公正を前にして冷淡な客観的姿勢を保ちうるとしたら、それは一種の共犯となるから。本書の最初から最後まで隅々にみなぎる激情は、公正さを求める激情、学生たちのデモと抗議を奮い立たせたのと同じ、燃えるような理想なのである。学生運動そのものと同様に、本書は特別の命題に支えられているわけではない。厳密な思想的方向性を提案しているのでもない。それどころか、その底に脈打つリズムは、鮮明にして抒情的かと思えば、薄暗く悲劇的でもあり、命そのものの律動である。
冒頭の雰囲気からは楽しげな熱狂と陶酔が伝わってくる。学生たちは街頭に打って出ると、集団行動、直接民主制、同胞愛の意味を発見する。こうしたものだけを武器に、彼らは弾圧と闘い、短期間で民衆の支援と忠誠を勝ち取ってゆく。ここまでのところ、エレナ・ポニアトウスカのこの物語は、若者世代の市民としての覚醒を語っている。ところが、上り調子のこの集団的白熱状態のストーリーは、ほどなくして陰惨な含みを帯びはじめる。すなわち、これら若者が象徴する希望の波と高邁な理想主義は、屹立する権力の壁を前に砕け散り、政府は残虐で暴力的な軍勢力を放ったのである。ストーリーは大虐殺に終わる。学生は為政者との公開対話を求めていたのに対し、後者は抗議の声を悉く黙らせるまでの暴力で応えたのである。それはなぜなのか。この虐殺の裏にあった理由は何なのか。メキシコ人はこのことを1968年10月以来自問しつづけてきた。その疑問が解かれたときはじめて、この国はその指導者と政治システムに信頼を取り戻すことができるのだろう。そうでなければ、メキシコは国としての自信回復を望めまい。
目隠しの男たちが作る歴史
ごく当初から学生たちは政治行動に特筆すべき才能を顕した。その運動に新しい息吹をもたらす方法として直接民主制というものをすぐさま発見した一方で、それを根本的源泉であるメキシコ国民全体との緊密な接触のもとに維持した。舞台裏での権力者間の取引と、政府重鎮の間で腐敗し共謀するリーダーによる陰での糸引きに慣れきった国で、学生は政府と公開対話を持つことを主張した。彼らの要求の控えめにして穏健な本質は、「民主化」という言葉で要約することができようが、それは1910年以来メキシコの民が心の底から切望してきたことだった。ところが、彼らの行動は本物の現実だったのだが、解釈は想像上の産物に過ぎなかった。彼らの多くは、1958年の鉄道員の運動と十年後の自分たちの運動の間には、直接の関連があると信じ込んでいた。しかし、そのために両運動間の目的と戦術の違い、そしてとりわけ、異なる階級構造を見落としていた。それゆえ、二つの事件の全く相異なる意味を認識していなかったのである。
メキシコ政府の態度は許し難いものですらあった。それは信じ難いほど盲目的で、聞く耳を持たぬものだった。メキシコ国の大統領および正式な権限を擁する政権党はメキシコ全体の権化であり、彼らこそがメキシコの過去、現在、未来なのだ。制度的革命党(PRI)は多数派政党なのではなく、満場一致そのものなのである。彼らに対する軍の攻撃は政治的行動であっただけではなく、いわば宗教的天罰の性格を帯びていた。神の復讐、懲戒罰、激怒した父なる全能神の教訓だったのである。この姿勢には深い歴史的ルーツがある。その起源は、この国のアステカ時代と植民地時代の過去に求められる。それはさらに、男性優位主義のべつの表現、とりわけメキシコの家族およびメキシコ社会における父親の卓越性の表われでもある。一口で言えば、1968年のメキシコでは、男たちがいま一度、目隠しされた状態で歴史を作ったのである。
露呈したもうひとつのメキシコ
1968年運動の背後には、夢からの、本物の繁栄と社会的調和という幻想からの、突然の目覚めがあった。1950年頃には、政治的安定、高い人口増加率にもかかわらず絶え間ない経済成長、目を見張る完璧なまでの公共事業プロジェクト、層の厚い中産階級の誕生、定職就業人口の増大と労働者階級の生活水準上昇、社会を覆う安穏の雰囲気、とあたかも各々のどの社会層にも完全なる意見の一致をみているかのような雰囲気が充満していた。1968年、この見せかけの合意は粉みじんになり、突如メキシコのもうひとつの顔が露呈した。憤慨する若者男女の世代と、四十年間国を支配していた政治システムに激しく反対を唱えた中間層である。1968年の騒乱は、発展した社会層と称されうるメキシコ社会の都市に住む中間層、全国人口の半分近くを占め、過去二、三十年間にますます急速な近代化を遂げた層の中で、深い亀裂を突如として暴露した。しかし、近代的で発展したメキシコの内部危機は、学生運動がその裏に隠れていたものを露わにしたとき、いっそう劇的で決定的な重大性を呈したのである。つまり、露呈したのは、もうひとつのメキシコ、何百万人という絶望的なまでに貧しい農民と、都市に移住し今日の新・根無し草(都会の砂漠をさまよう放浪者)となった失業者の大群だった。
1968年運動にはいかなるイデオロギーもなかった。政治システムの麻痺と少数者にしか恩恵を与えない「開発」政策への強い不満こそが、国を「民主化」しようという学生の呼びかけに都市住民層の大部分が即座に呼応した理由である。メキシコにおいて民主主義の伝統を構築してゆくことは、経済発展や、真の平等に到達するための闘いと同じくらい重要かつ緊要な課題である。
真の解決策は、PRIとは全く違った、他の選択肢を生み出すことだ。「民主化」は今も、正当な要求、かつ差し迫った課題なのである。変革を熱望する集団は、自らの民主化、すなわち自由な批判と討論を自らの組織内部で常習化するよう、一歩を踏み出すことから始めるべきであろう。(訳・北條ゆかり)
(Octavio Paz/詩人・批評家)
※全文は『トラテロルコの夜』に掲載