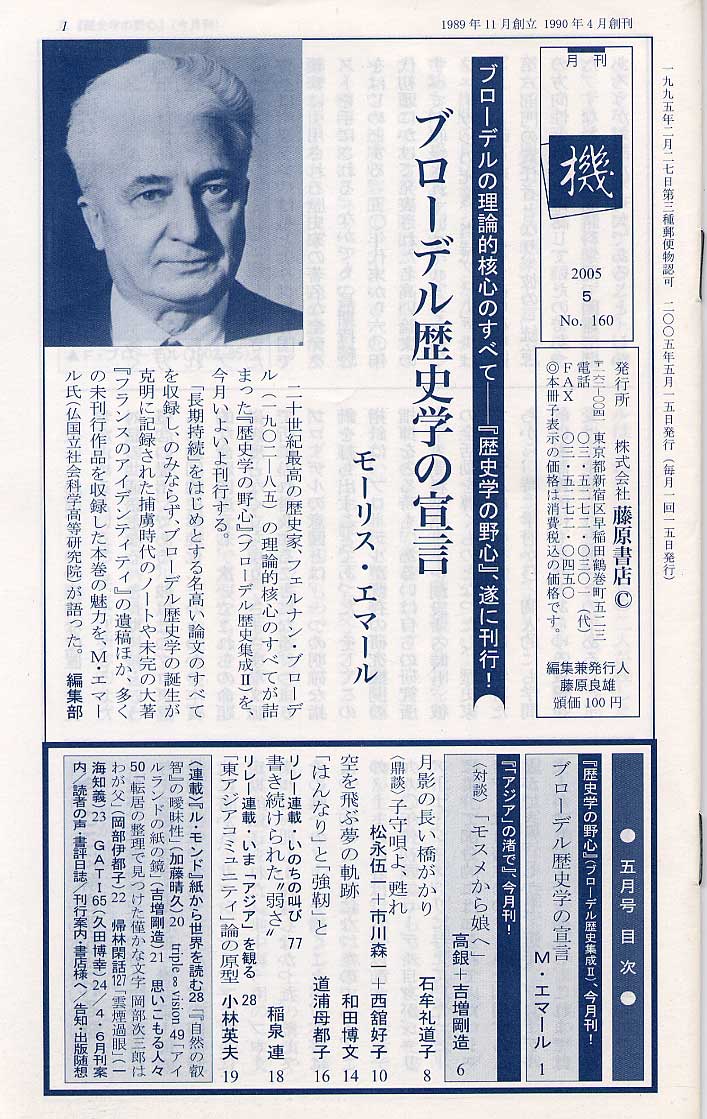人の心のかそけきところを見落しては来なかっただろうか。かそけき声を聴き落しては来なかっただろうか。既成の浅薄な世界観にすっぽりとらわれてはいなかっただろうか。
そんな気持をずうっと持ち続けていた。さかのぼれるかぎり隅々まで点検し、自分のコスモスを描出し直したいと希いながらこのような作品になった。
天からえらばれた村
作品の登場人物は、ふつう作者の分身だと考えられるけれども、『天湖』の場合のように自らつよくそれを感じたことはなかった。みんな、人間としては出来そこなっているわたしがつくり出した人形である。
この人形たちの背中を押し、謡わせているのは、奥深い山々の気配だとおもう。九州山地から流れ下る緑川、球磨川、耳川というのがある。緑川の源流には穿の宮と名づけられた洞穴が口をひらいていて、見るからにおそろしい。土地の人たちは昔からその奥には人跡未踏の湖があるのだと信じ、注連縄を張り、近づかない由である。大蛇の棲家かもしれない。天湖というイメージをそこから貰うことにした。九州山地の奥の院は人跡未踏のここだと思ったからである。村の名を天底とした。天からえらばれた村の意である。
汚濁の沼の住民
ダムの底に沈められた小さな村のことを、私は具体的には知らない。僅かに聞いて切ないのは、もとの村民たちが平地に下り、時々出逢っては、沈められた村の思い出を語りあうというその様子である。
「夢にみるのは育った里のことばかり」
というのがまず口に出るという。その人たち一代ではなく、三代前、五代前とさかのぼって、遠い昔から受け継がれ、ほとんど無意識化された山里の生活習慣やことば、ひとさまに対する心づかいなどがあったにちがいない。ほとんど秘境に近い山里の、日本人にとっては、失ってはならない宝ともいえる心性がそこに遺っていたのではなかったか。
自分を含めて、平地に下った人間社会の平板で浅薄な様相がつくづくかえりみられる。わたしたちは生まれたての山霧の精だったようなヒトに帰れるだろうか。そこから生じる声やことばをとり戻すことができるだろうか。街の汚れを脱ぎ捨てられるだろうか。汚辱の沼となり果てたわたしたちの現代。頭上も肩先も両脇もだぶだぶの汚気にまみれ、息を僅かに吐きながら歩いている。互いが誰だか、たぶんわからない。
汚濁の沼の住民であるわたしたち。沼を形づくっているさまざまの因子。それらは一見明度を保っているかに思えるけれども、すべてわたしたち人間の心の内から溶出し、化学作用をおこしている悪液ではないだろうか。わたしたちはそのことにたいそう慣れてきて、たぶん免疫とやらも身につけつつあるのだろう。とても危ないと思う。ヒトとしてもっとも柔らかいデリケートな感受性や、倫理性をなくした棒切れのような、血のうすい人格に変えられてゆく。
月影の長い橋がかり
朝昼晩テレビの画面いっぱいに飛散する人間の血しぶき。かりにそれが絵の具であったにしても、これから育つ子どもらは毎日毎日、返り血を浴びて育つようなものだ。この犯罪博物列島で育つ子らの行く末こそおそろしい。
自分の思索の源流を探して天底の世界をしつらえたけれども、近ごろはまた、ここからの出口がうまく見つからない。そんな気持の中で小暗い通路をみつけてゆくと渚に出た。そこで僅かに天啓のようなものを感じて新作能『不知火』をしあげた。
今おもえば、『天湖』という作品は、『不知火』へゆくまでの、月影の長い橋がかりのようなものかもしれない。
(いしむれ・みちこ/作家)
※全文は『天湖ほか』に掲載(構成・編集部)